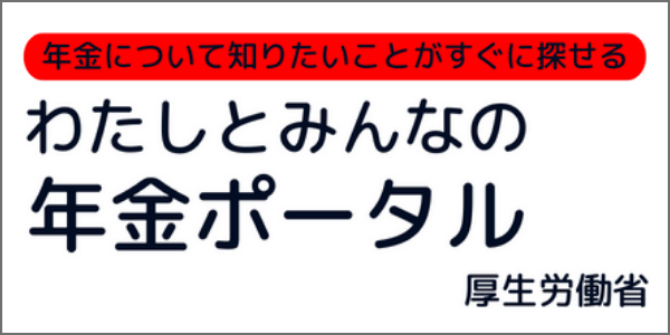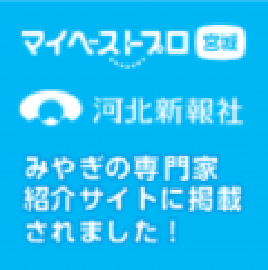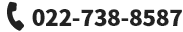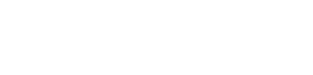106万円・130万円の壁にどう向き合う?第3号被保険者から厚生年金に切り替える意味とは
106万円(正確には105万6千円)・130万円の壁が注目される中、配偶者の扶養から外れることに不安を感じている方も多いはず。今回は「年金制度の視点」で、厚生年金(第2号被保険者)に切り替えるメリットを専門家がわかりやすく解説します。
年収の壁と「扶養」の誤解?
近年話題になっている「106万円の壁」「130万円の壁」。これらは税制上の話と混同されがちですが、実は年金や健康保険など社会保険制度の話が本質です。特に国民年金の第3号被保険者として扶養に入っている方にとって、これらの壁は「将来の保障」にも直結する大切なテーマです。
第3号被保険者とは?
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の方で、年収130万円未満(※)である場合に該当します。この制度により、自身で保険料を支払うことなく、将来の老齢基礎年金を受給することが可能です。
※2024年10月からは「従業員51人以上」の企業で、一定条件を満たす場合に年収106万円以上で自動的に厚生年金・健康保険の加入対象となり、第3号から外れます。さらに今後は企業規模要件が段階的に撤廃され、2035年10月には全企業に適用される予定です。
106万円・130万円の壁とは?
【106万円の壁】
2024年10月から、従業員51人以上の企業で週20時間以上・標準報酬月額など一定条件を満たす方が、年収106万円を超えると厚生年金・健康保険の加入義務が発生します。
【130万円の壁】
中小企業や個人事業主など、社会保険の加入義務がない職場で働いている場合でも、年収130万円を超えると扶養から外れ、自ら国民年金・国保に加入する必要があります。
このように、勤務先や働き方によって適用制度が大きく異なります。
第2号被保険者になる“メリット”とは?
年収が上がって扶養から外れると「損では?」と感じるかもしれません。しかし、厚生年金(第2号被保険者)に切り替えることで得られる保障や将来の年金額の違いは見逃せません。
◯ 将来の年金額が増える
「老齢厚生年金」は「報酬比例部分」があるため、働いている間の収入に応じて年金額が「老齢基礎年金」に上乗せされる仕組みです。短時間勤務でも一定の収入があれば、「老齢厚生年金」に反映されます。
◯ 障害厚生年金の対象になる
初診日が厚生年金に加入している間に病気や事故で障害が残った場合、「障害厚生年金」の支給対象になります。「障害基礎年金」と異なり「3級」でも支給される可能性があり、軽度の障害でも年金を受給できる可能性があります。
また、「2級以上」に該当した場合は、一定の要件を満たすと「加給年金(配偶者と子の加算)」が支給されることもあります。
※初診日が第3号被保険者の方が受給できる障害年金は、「障害基礎年金」となり、子の加算だけで配偶者加算はありません。
◯ 健康保険の保障が拡充される
厚生年金に加入すると、同時に被用者保険(協会けんぽなど)にも加入します。これにより以下のような保障が受けられます:
・高額療養費制度:医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻されます(第3号被保険者=扶養でも対象)。
・出産育児一時金:第3号でも受給可能です。
・傷病手当金・出産手当金:これらは第3号では対象外ですが、厚生年金加入者(第2号)なら自身が被保険者となるため支給対象になります。
「保険料を払う=損」ではない
たしかに、厚生年金に加入すれば、保険料負担が発生します。しかしその一方で、一定の要件のもと将来の年金額増加、障害年金の保障拡充、私傷病による休業時の給付などの手厚さなど、多くの“見えない安心”が得られます。
将来の安心は「今の選択」から始まる
106万円や130万円の壁を意識しすぎるあまり、必要以上に労働をセーブしてしまうのは、本当に損かもしれません。特に障害年金や将来の老齢年金といった視点から見ると、第2号被保険者になることは「将来への備え」そのものです。
「今の自分には関係ない」と思っていても、「いつか」必要になるかもしれない社会保険。その「いつか」は、今日・明日かもしれません!
だからこそ、しっかりと仕組みを理解したうえで、自分にとってベストな働き方を選ぶことが大切です。

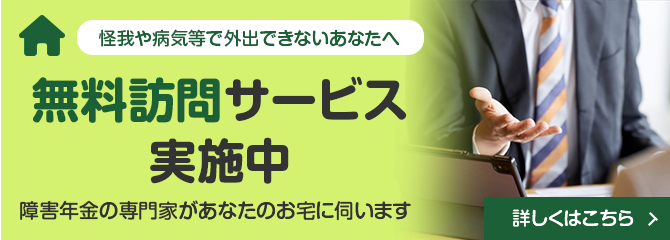
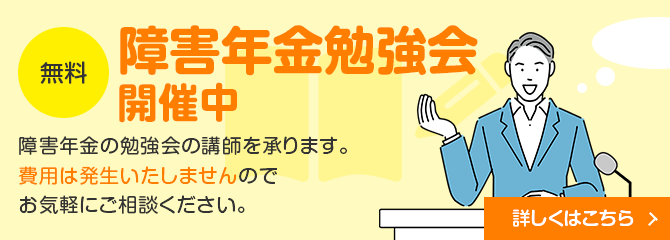

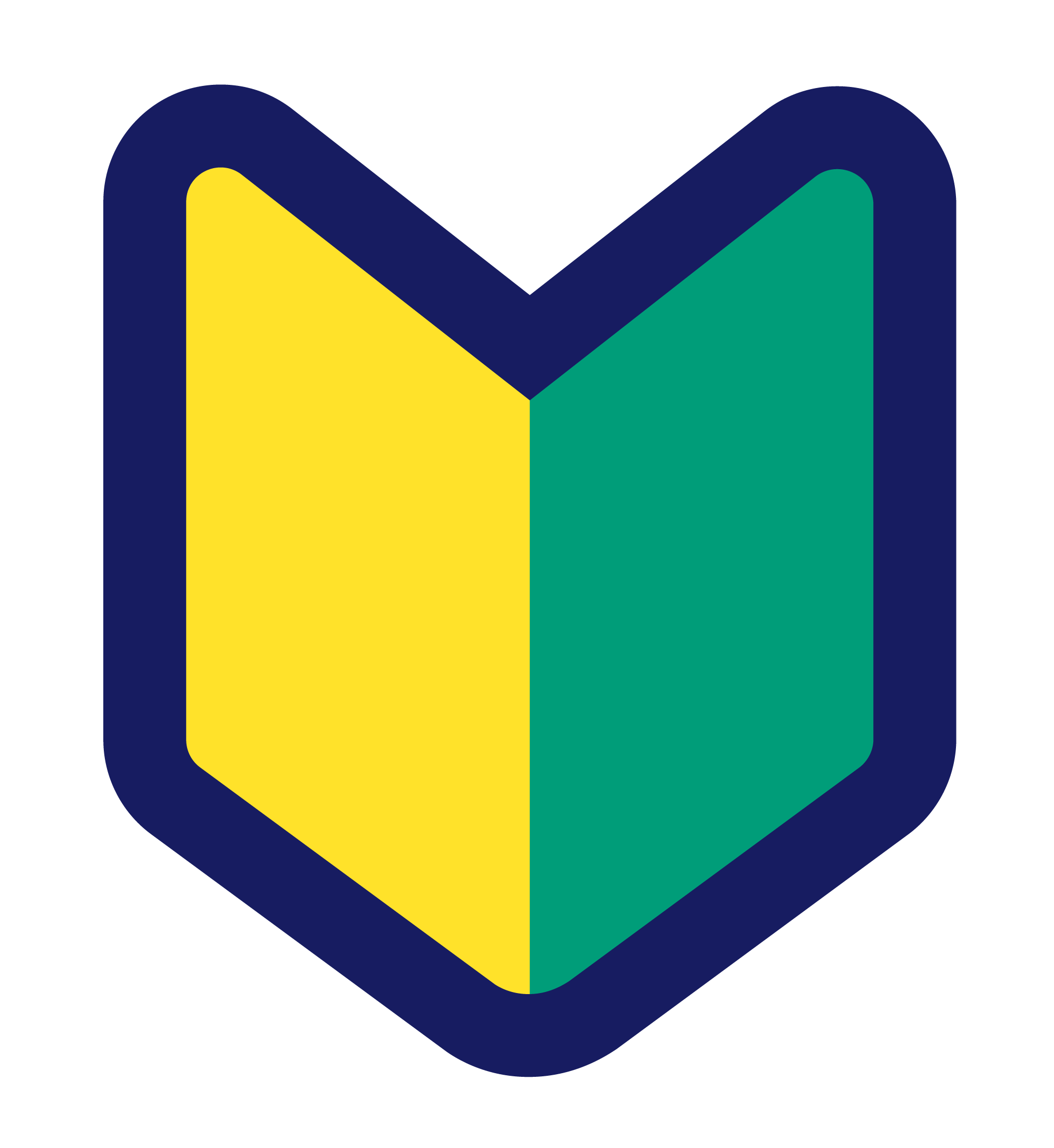 初めての方へ
初めての方へ