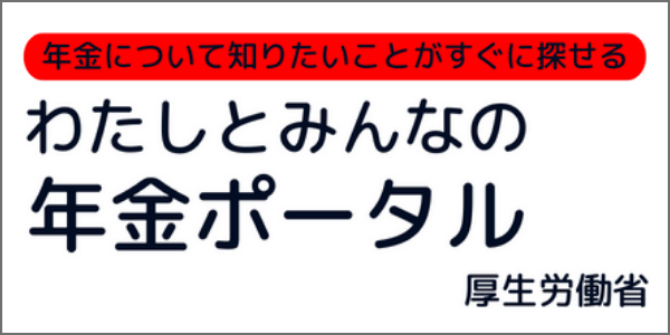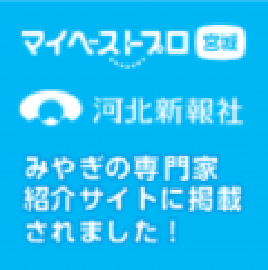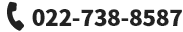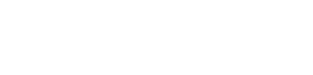「 高次脳機能障害」と障害年金申請の流れとポイント
高次脳機能障害とは?
高次脳機能障害とは、脳の損傷によって記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知機能の低下が生じる状態を指します。事故や脳卒中(脳梗塞・脳出血)、脳腫瘍などが原因で発症し、外見上は健常者と変わらないため、周囲から理解されにくい障害です。
〇記憶障害:新しいことを覚えられない、過去の出来事を忘れるなどの症状があり、日常生活や仕事に大きな支障をきたします。
〇注意障害:集中力が続かない、気が散りやすいなどの症状があり、作業のミスが増えたり、物事を途中で放棄してしまうことがあります。
〇遂行機能障害:計画を立てたり、順序立てて物事を進めることが難しくなり、日常の家事や仕事の遂行に問題が生じます。
〇社会的行動障害:適切なコミュニケーションが取れない、感情のコントロールができないなどの問題が生じ、人間関係に影響を与えます。
高次脳機能障害で障害年金が認定されるのか?
高次脳機能障害でも、日常生活や就労が困難な場合には、障害年金を受給できる可能性があります。障害年金には、国民年金の「障害基礎年金」と厚生年金の「障害厚生年金」があり、認定基準を満たせば受給対象となります。
障害年金の等級と認定基準
高次脳機能障害は、障害年金の「器質性精神障害」として、診断書に種類は「精神の障害用」を使用します。
・1級:日常生活のほぼすべての動作に介助が必要な状態。
・2級:日常生活に著しい制限があり、常に支援が必要な状態。
・3級:(厚生年金のみ):労働が著しく制限される状態。
特に、記憶障害や注意障害、遂行機能障害が重度である場合、2級以上に認定される可能性が高いとされています。
障害年金申請の流れのポイント
1. 初診日の証明
障害年金の申請には、障害の原因となった病気やけがの初診日が必要です。脳卒中などで長期間入院していた場合、発症時に最初に診療を受けた医療機関から「受診状況等証明書」を取得することが求められます。
2. 診断書の作成
医師に診断書を作成してもらう際、障害年金の申請には「精神の障害用」の診断書を使用する必要があります。以下の点を詳しく記載してもらうと認定の可能性が高まります。
〇記憶障害、注意障害、遂行機能障害の具体的な影響
〇日常生活での支障(食事、着替え、金銭管理など)
〇家族や支援者の援助がどの程度必要か
3. 日常生活の証明
障害認定では「できること」よりも「できないこと」が重視されます。家族や支援者による日常生活の記録や、第三者の証明(介護者の意見書など)を用意すると、より有利になります。
4. 申請手続き
・障害認定日請求:初診日から1年6か月経過した時点での診断書を提出
・事後重症請求:症状が進行し、障害等級に該当した時点で請求
障害基礎年金は1級・2級のみが対象で、障害厚生年金は3級まで適用されます。
まとめ
「高次脳機能障害」は外見では分かりにくいため、申請の際には具体的な症状と生活への影響を詳細に伝えることが重要です。専門家のサポートを受けながら、適切な書類を準備し、スムーズな申請を目指しましょう。
障害年金の申請に関して不安がある方は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

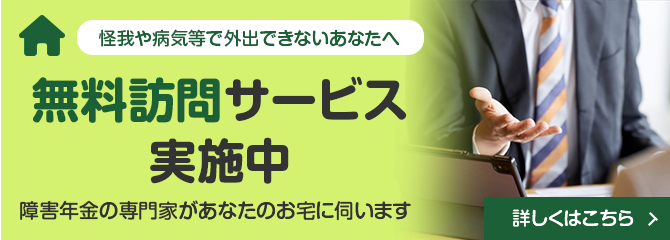
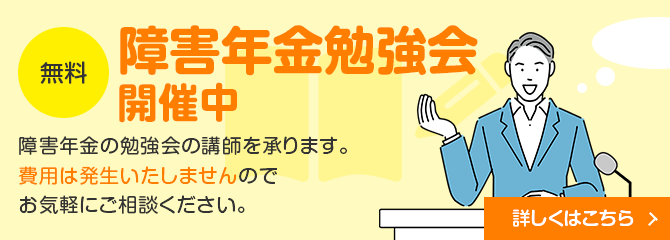

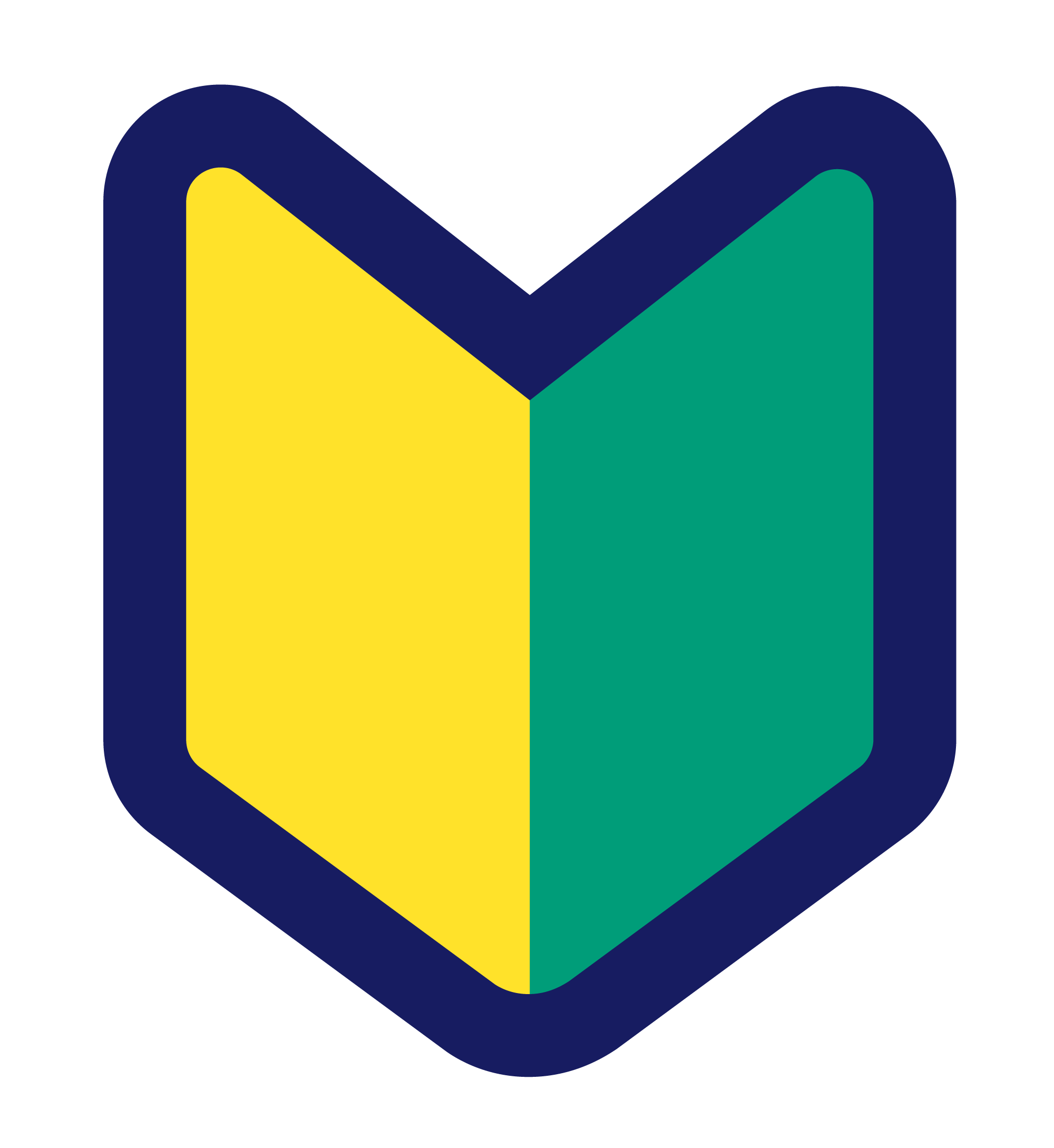 初めての方へ
初めての方へ