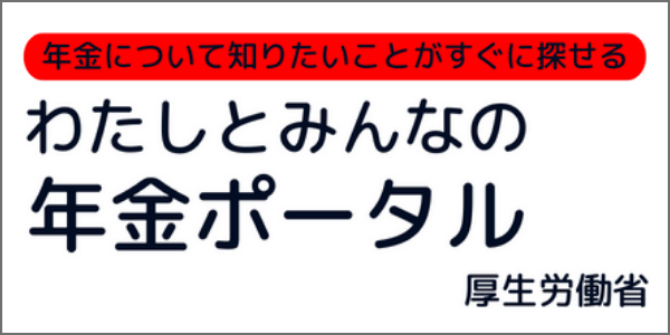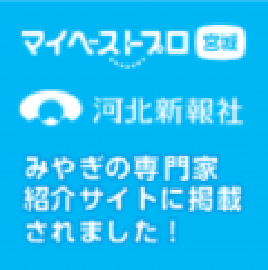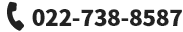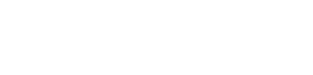「腎疾患」の特徴と障害年金との関係
目次
腎疾患と一口に言っても、その種類や進行度、日常生活への影響はさまざまです。以下では、障害年金の対象となりやすい代表的な腎疾患について、それぞれの特徴と障害年金申請時のポイントを解説します。
糖尿病性腎症
腎臓は、血液中の老廃物や余分な水分をろ過して尿として排出する重要な臓器です。腎臓の中には、毛細血管が球状に集まった「糸球体(しきゅうたい)」という部分があり、ここで血液がろ過されます。糖尿病性腎症は、高血糖によってこの糸球体の血管が傷つき、ろ過機能が低下することで発症します。初期には自覚症状がほとんどなく、病気が進行してから症状が現れることが多いのが特徴です。
慢性腎炎
腎臓には、血液中の老廃物や余分な水分をろ過して尿を作る「糸球体」という小さなフィルターが無数にあります。慢性腎炎は、この糸球体に持続的な炎症が起こることで、フィルターとしての機能が徐々に損なわれていく病気です。炎症の原因は様々ですが、多くの場合、免疫の異常が関与していると考えられています。初期には自覚症状がほとんどなく、健康診断などで尿異常(タンパク尿や血尿)を指摘されて発見されることが多いです。
ネフローゼ症候群
ネフローゼ症候群は、腎臓の糸球体(血液をろ過するフィルター)に異常が生じ、大量のタンパク質が尿中に漏れ出し、その結果として体内に様々な症状が現れる病態を指します。病気の名前ではなく、特定の症状の組み合わせ(症候群)を指す言葉です。
腎硬化症
腎臓は、全身の血液をろ過し、老廃物や余分な水分を尿として排出する重要な臓器です。腎臓の中には、非常に細い血管が多数存在し、これらが正常に機能することで血液のろ過が行われます。腎硬化症は、長期間にわたる高血圧によって、これらの細い血管(腎臓内の動脈)が動脈硬化を起こし、血管の壁が厚くなったり、硬くなったりして、血液の流れが悪くなることで発症します。血流が悪くなると、腎臓の細胞に十分な酸素や栄養が届かなくなり、腎臓の機能が徐々に低下していきます。
多発性嚢胞腎
腎臓の内部に、本来はないはずの嚢胞が多数発生し、それが時間とともに大きくなり、数も増えていくことで、腎臓全体が腫大し、正常な腎臓の働き(血液のろ過、老廃物の排出、血圧の調整など)が妨げられる病気です。腎臓だけでなく、肝臓、膵臓、脾臓など、他の臓器にも嚢胞ができることがあります。
急速進行性腎炎
腎臓の糸球体(血液をろ過するフィルター)に炎症が起こり、数週間から数ヶ月という比較的短い期間で急速に腎機能が低下していく重篤な病気です。放置すると、短期間で末期腎不全に至り、透析が必要になる可能性があります。
腎盂腎炎
腎盂腎炎(じんうじんえん)は、腎臓の「腎盂(じんう)」という部分と、その周囲の腎臓組織に細菌が感染して炎症を起こす病気です。尿路感染症の一種で、膀胱炎が悪化して細菌が腎臓まで上行することで発症することが多いです。
膠原病に伴う腎障害(ループス腎炎など)
膠原病(こうげんびょう)は、全身の様々な臓器に炎症を引き起こす自己免疫疾患の総称です。免疫システムが異常をきたし、自分の体の組織を誤って攻撃してしまうことで発症します。この膠原病が原因で腎臓に障害が生じることを「膠原病に伴う腎障害」と呼び、その代表的なものが「ループス腎炎」です。ループス腎炎は、全身性エリテマトーデス(SLE)の患者さんの約半数以上が発症すると言われる、最も頻度の高い膠原病に伴う腎障害です。SLEの予後を大きく左右する重要な合併症であり、腎臓内科とリウマチ・膠原病内科が連携して診療にあたります。
アミロイドーシスによる腎障害
アミロイドーシスは、特定の異常なタンパク質(アミロイド線維)が全身の様々な臓器や組織に沈着し、その臓器の機能障害を引き起こす病気の総称です。腎臓はアミロイドが沈着しやすい臓器の一つであり、アミロイドが腎臓に沈着することで腎機能が低下することを「アミロイドーシスによる腎障害」と呼びます。
初診日と納付要件
障害年金の受給には、「初診日」の証明が必要です。初診日とは、腎疾患について初めて医師の診療を受けた日です。また、その初診日の前日時点で、一定の年金保険料納付要件を満たしている必要があります。
申請時の注意点
腎疾患で障害年金を申請する際は、以下の点に注意しましょう。
診断書の記載内容:透析の実施状況や腎機能数値(クレアチニンクリアランス、GFR値など)、日常生活への影響を明確に記載してもらう必要があります。
日常生活の制限状況:自力での食事や排泄、通院などにどれほど支障があるかを記録・申告することが大切です。
初診日から1年6カ月を経過した日以降に、人工透析開始になった方は、その事実だけで障害年金等級2級認定となります。ただし、初診日から1年6カ月経過していない場合は、人口透析開始日から3カ月を経過した日に2級認定となります。
社会保険労務士に相談するメリット
腎疾患は医療情報や日常生活状況の伝え方によって、障害等級の判定が大きく変わります。社会保険労務士に相談することで、適切な診断書の取得方法や申請書類の整備など、受給に向けた具体的な支援を受けることができます。
まとめ
腎疾患による障害年金は、透析の有無や腎機能の低下度合い、日常生活の制限度合いによって、等級や受給可否が決まります。初診日の確認や適切な診断書の準備が受給の鍵となるため、迷わず専門家に相談することをおすすめします。

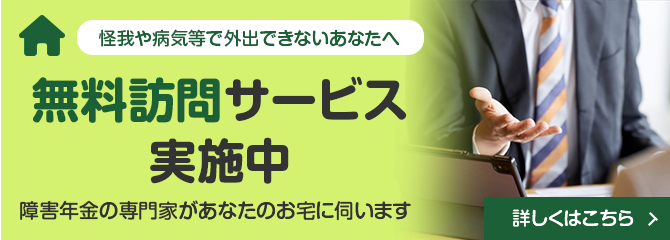
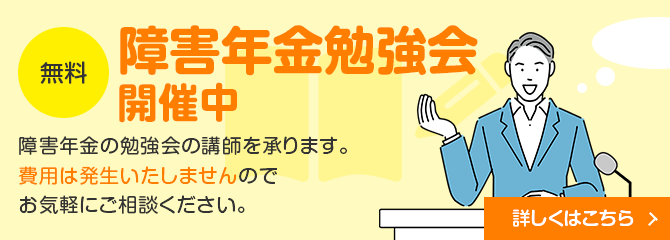

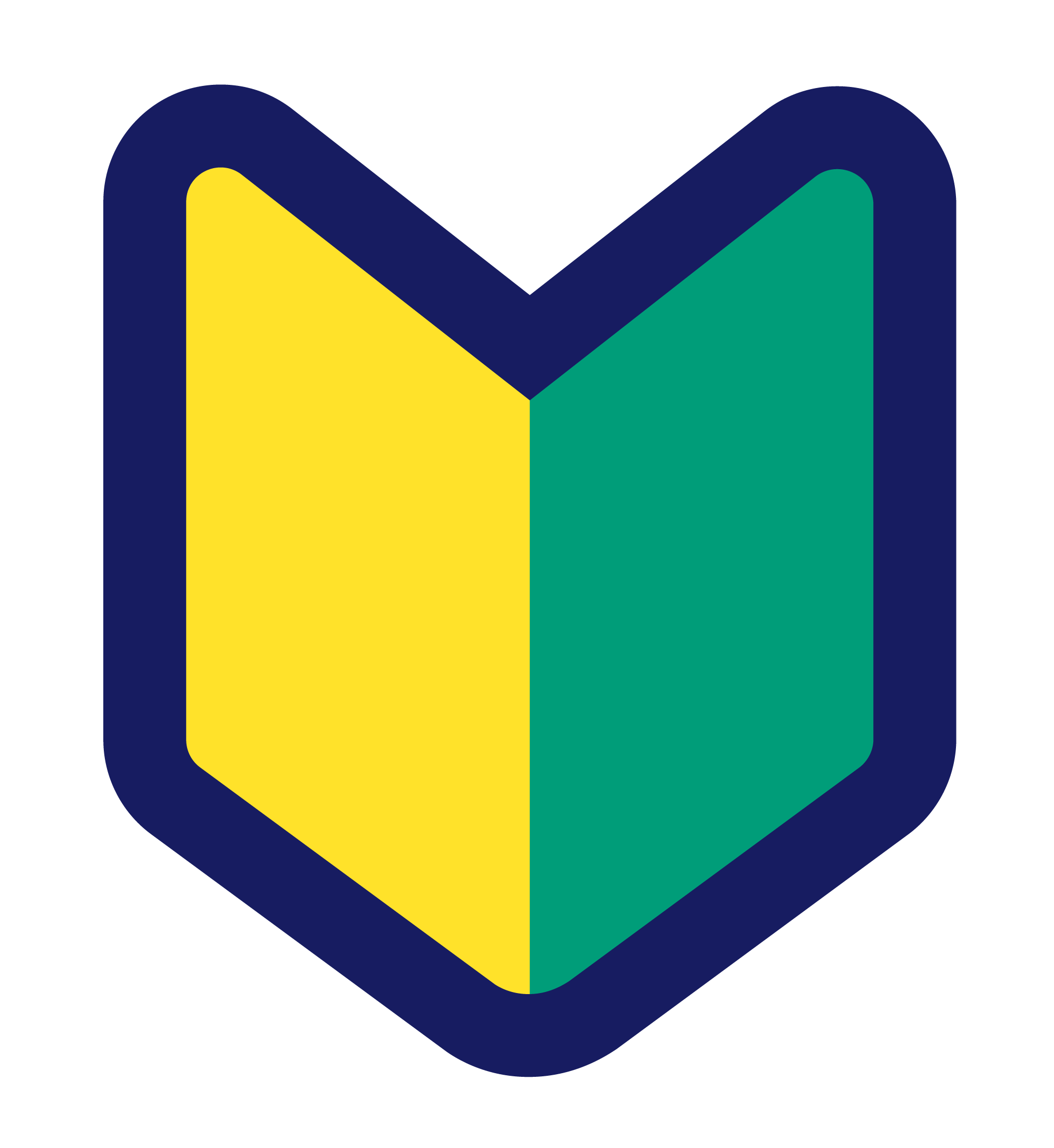 初めての方へ
初めての方へ