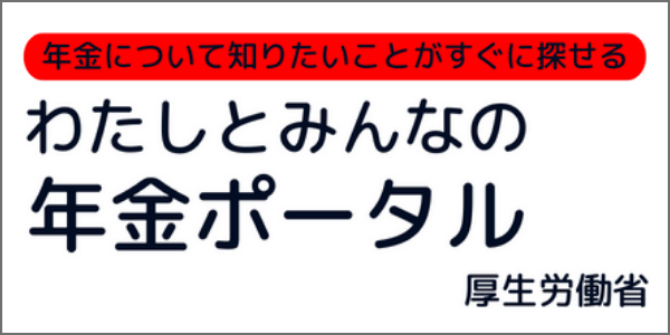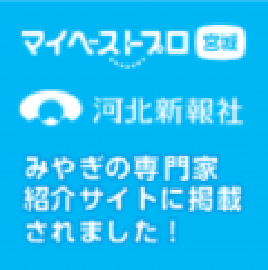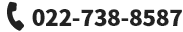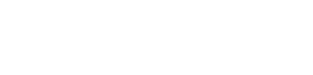「病歴就労状況等申立書」の重要性が増す今、記載すべき具体的な内容とは?
目次
障害年金の申請で必要な「病歴就労状況等申立書」。令和6年度は特に審査が厳格化され、具体的な生活・就労状況の記載が求められています。記載ポイントと注意点を解説します。
病歴就労状況等申立書とは
障害年金を申請する際に提出する「病歴就労状況等申立書」は、発病から初診、現在に至るまでの病歴や生活の実態、就労の有無や状況を本人の言葉で記載する重要な書類です。
この書類は単なる補助的なものではなく、医師の診断書や受診状況等証明書と同等に、審査に大きく影響する重要資料です。
令和6年度、審査現場での変化:照会の増加
令和6年度に入り、日本年金機構からの照会内容が大幅に詳細化しています。特に精神疾患に関する申請では、診断書の記載と申立書の記載に齟齬があると、照会が行われるケースが非常に増えています。
実際に多くの申請者に対して以下のような詳細な生活状況や就労状況に関する照会が行われており、これらを最初から申立書に丁寧に記載しておくことが求められています。
記載が求められる生活状況の項目
精神疾患などで障害年金を申請する場合、次のような項目について、「一人でできないため、周囲の援助を受けていること」「援助の内容や頻度」を明確に記載する必要があります。
- 適切な食事:食事の準備や摂取に支障がないか、偏食や過食・拒食があるか
- 身辺の清潔保持:入浴・洗顔・着替え・歯磨きなどを自力で行えているか
- 金銭管理と買い物:必要な金銭の計算や管理ができるか、外出しての買い物が可能か
- 通院と服薬:自発的な通院や服薬ができるか、誰かの付き添いや声かけが必要か
- 意思伝達・対人関係:他人とスムーズに意思疎通ができるか、トラブルや妄想、幻聴などはないか
- 身辺の安全保持と危機対応:火の元の管理、金銭トラブル、過剰反応やパニックへの対処力など
- 社会・趣味活動への参加:趣味や興味を持ち、それに取り組めるか、外出頻度や活動内容
これらの項目について、「できない」だけではなく、「どういった援助を受けているか」「援助の頻度や方法」まで記載することが極めて重要です。
就労状況について求められる詳細情報
就労中の申請者に対しては、「働いている=障害が軽い」と誤解されがちですが、実際には「就労の形態」や「配慮の有無」が重要です。そのため、以下の点を具体的に記載する必要があります:
- 職種と雇用形態(例:清掃業/短時間アルバイト)
- 勤務時間と日数(例:週3日、1日4時間)
- 給与額
- 通勤手段と所要時間
- 仕事の具体的な内容
- 他の従業員とのコミュニケーション状況(会話があるか、孤立しているかなど)
- 職場での配慮内容(ミスをフォローする上司の存在、休憩の配慮など)
- 専門職・家族からの支援(通院同行、生活指導、服薬管理、就労支援機関の関与など)
これらの情報が明確であればあるほど、審査側も障害の影響を具体的に把握しやすくなり、診断書との整合性が取りやすくなります。
病歴就労状況等申立書の記載が重要な理由
- 生活状況や日常動作の具体性が、障害の程度を判断する材料となる
- 診断書との整合性が審査の肝となる
- 「できること」ではなく「できないこと・援助が必要なこと」が審査基準
- 働いている場合は、配慮や支援の詳細まで示すことで不支給リスクを下げられる
社会保険労務士への相談で申請成功率を高める
病歴就労状況等申立書の記載は一見簡単そうに見えて、実は非常に難しく、一語一句が審査結果に影響を与えることもあります。ご自身の症状や状況をうまく言語化できない場合、専門の社会保険労務士に相談することで、状況に応じた適切な記載が可能になります。
まとめ
令障害年金の審査現場では「病歴就労状況等申立書」の重要性がますます高まっています。形式的な記載ではなく、具体的な生活・就労実態とその支援状況を丁寧に記すことが、障害の程度を正確に伝える鍵となります。
少しでも不安がある方は、専門家と連携し、適切な申請準備を進めていきましょう。
仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「仙台障害年金相談オフィス」にお任せください。仙台市中心に宮城県全域を障害年金専門社労士があなたの障害年金受給を徹底サポートします。

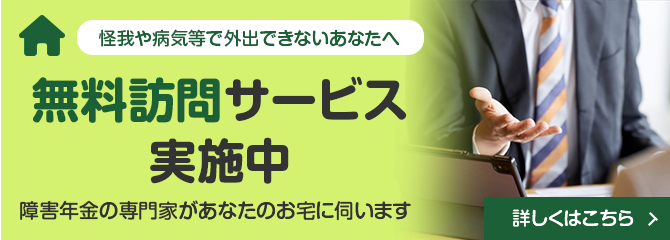
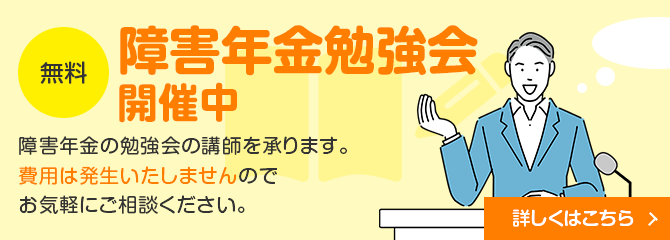

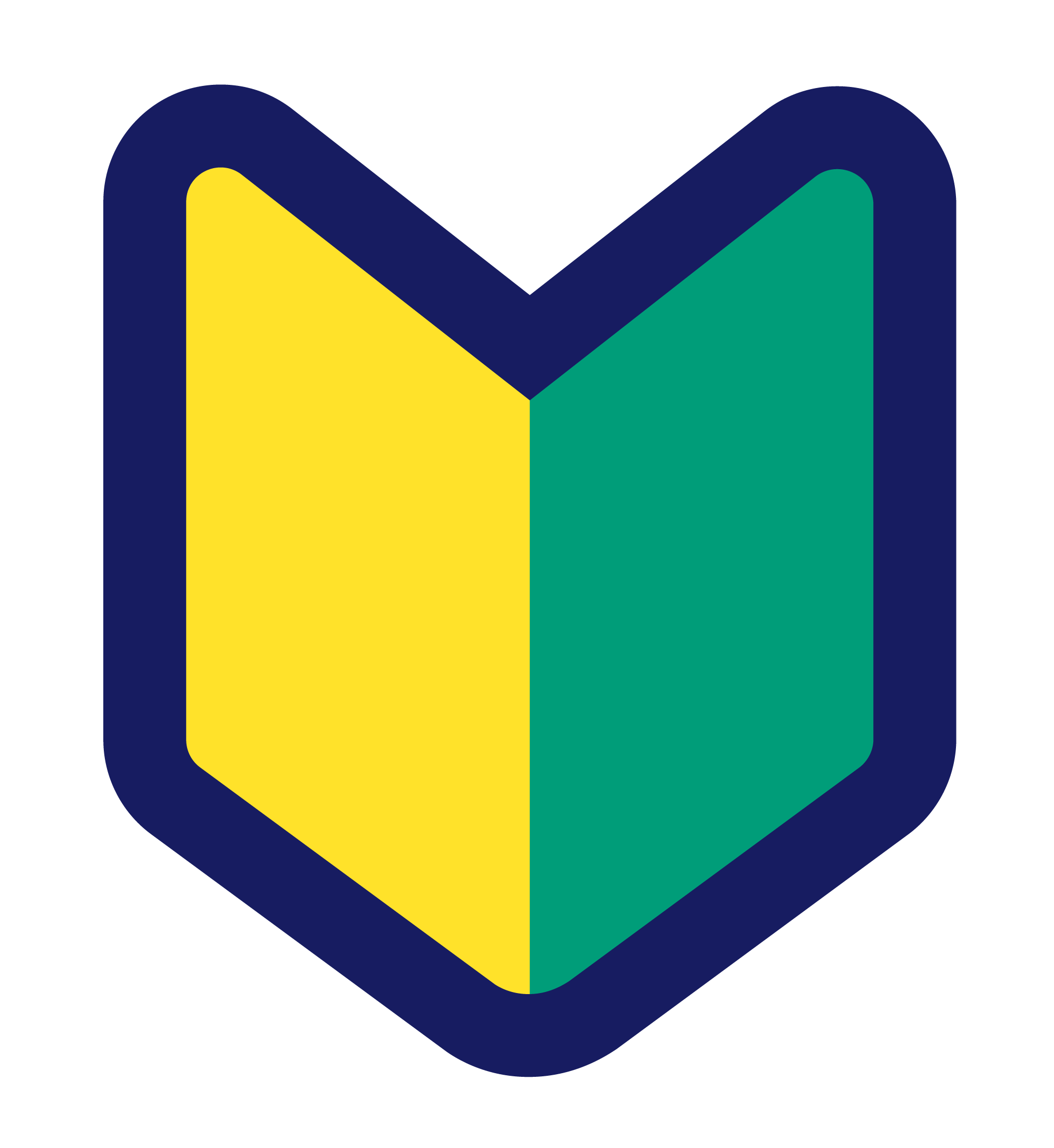 初めての方へ
初めての方へ