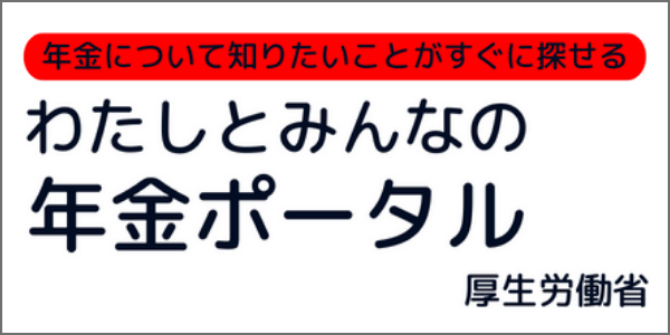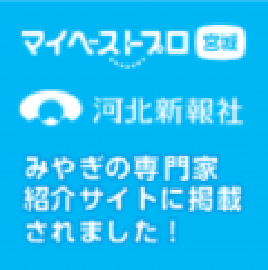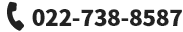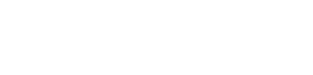「人工肛門」・「新膀胱造」設後に障害年金は受給できる?認定基準と申請時の注意点を詳しく解説
目次
人工肛門や新膀胱造設、尿路変更術、完全排尿障害に関する障害年金の認定基準をわかりやすく解説。申請タイミングや注意点も詳しくご紹介します。
人工肛門・新膀胱造設・尿路変更術とは
人工肛門(ストマ)とは、大腸や直腸などに障害が生じ、自然排便が困難になった場合に、腹部に便を排泄するための新たな出口を作る手術です。
また、膀胱を摘出した場合には新膀胱造設や尿路変更術を行い、尿を体外へ排出する仕組みを再構築します。
これらの手術は、排泄機能に恒久的な影響を及ぼすため、障害年金の対象となる可能性があります。
人工肛門や新膀胱造設後の障害年金認定基準
障害年金における人工肛門・新膀胱・尿路変更の認定基準は、以下の通り明確に定められています。
3級に認定されるケース
初診日が障害厚生年金被保険者の場合
- 「人工肛門」を造設した場合
- 「新膀胱」を造設した場合
- 「尿路変更術」を施した場合
これら単独であれば、原則、障害厚生年金3級に認定されます。
3級とは、労働に著しい制限を受けるか、著しい制限を加える必要がある状態を意味します。
2級に認定されるケース
以下に該当する場合は、より重度な障害とみなされ、障害厚生年金、又は、障害基礎年金2級認定となります。
- 「人工肛門」を造設し、かつ「新膀胱」を造設した場合
- 「人工肛門」を造設し、かつ「尿路変更術」を施した場合
- 「人工肛門」を造設し、かつ「完全排尿障害(常時カテーテル留置または自己導尿が必要な状態)」に至った場合
2級は、日常生活に著しい制限があり、労働による収入を得ることが困難な状態を指します。さらに、手術後の全身状態や原疾患の進行状況等を考慮し、特に症状が重篤な場合は、さらに上位等級(例:1級)に認定されることもあります。
障害年金の認定時期について
障害年金の「障害認定日」は、障害の程度を判断する基準日であり、手術内容によって異なります。
通常の場合(3級対象)※初診日が障害厚生年金被保険者の場合
「人工肛門造設日」「新膀胱造設日」または「尿路変更術施行日」から6か月経過後、ただし、造設日・施行日が、初診日から1年6か月を経過している場合は、造設日・施行日から6カ月を経過していなくても、請求は可能です。
2級該当の場合(複合手術または完全排尿障害)
人工肛門+新膀胱造設の場合
→ 人工肛門造設日から6か月後または新膀胱造設日のいずれか遅い日を起算
人工肛門+尿路変更術の場合
→ それぞれの手術日から6か月経過後(いずれか遅い日を起算)
人工肛門+完全排尿障害の場合
→ 人工肛門造設日または完全排尿障害に至った日のいずれか遅い日から6か月経過後
この認定時期を正しく押さえていないと、申請が却下されたり、受給開始が遅れる恐れがあるため、特に注意が必要です。
申請時の重要ポイント
障害年金を申請する際は、次の点に十分注意しましょう。
〇診断書には詳細な記載を
排便・排尿機能の具体的な制限内容、日常生活への影響度、常時自己導尿やカテーテル留置の必要性などを、医師にしっかり記載してもらう必要があります。
〇初診日の証明を正確に
初診日の確定は、年金受給可否に直結します。初診にかかった医療機関の記録など、客観的資料を集めておきましょう。
〇提出書類を正確に整える
障害年金の請求には、診断書、病歴・就労状況等申立書、年金記録関連書類などが必要です。不備があると手続きに遅れが生じます。
専門家に相談するメリット
人工肛門・新膀胱造設後の障害年金申請は、医学的知識と法律知識の両方が必要になります。社会保険労務士に相談すれば、適切な等級認定を見据えた書類作成、不支給リスクの軽減、スムーズな申請サポートが受けられ、結果的に安心して年金受給を目指すことができます。
まとめ
人工肛門や新膀胱造設、尿路変更術、完全排尿障害がある場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。手術内容やその後の生活状況によって、2級・3級と認定等級が変わりますので、正しい知識を持って申請を行うことが重要です。
もしご自身だけで手続きに不安がある場合は、社会保険労務士へのご相談をおすすめします。専門家の力を借りて、確実に権利を守りましょう。

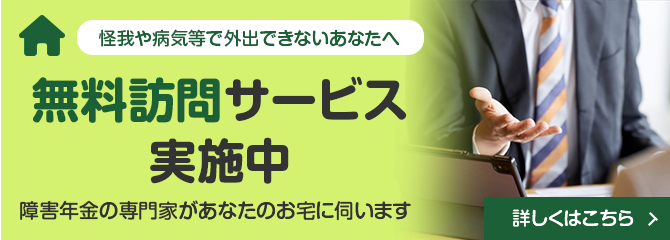
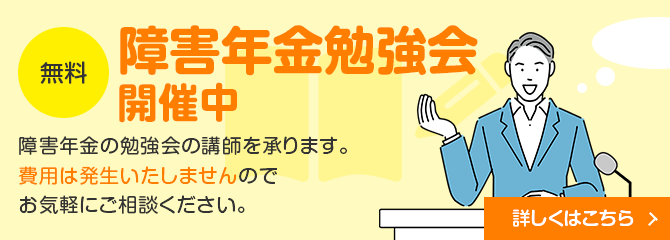

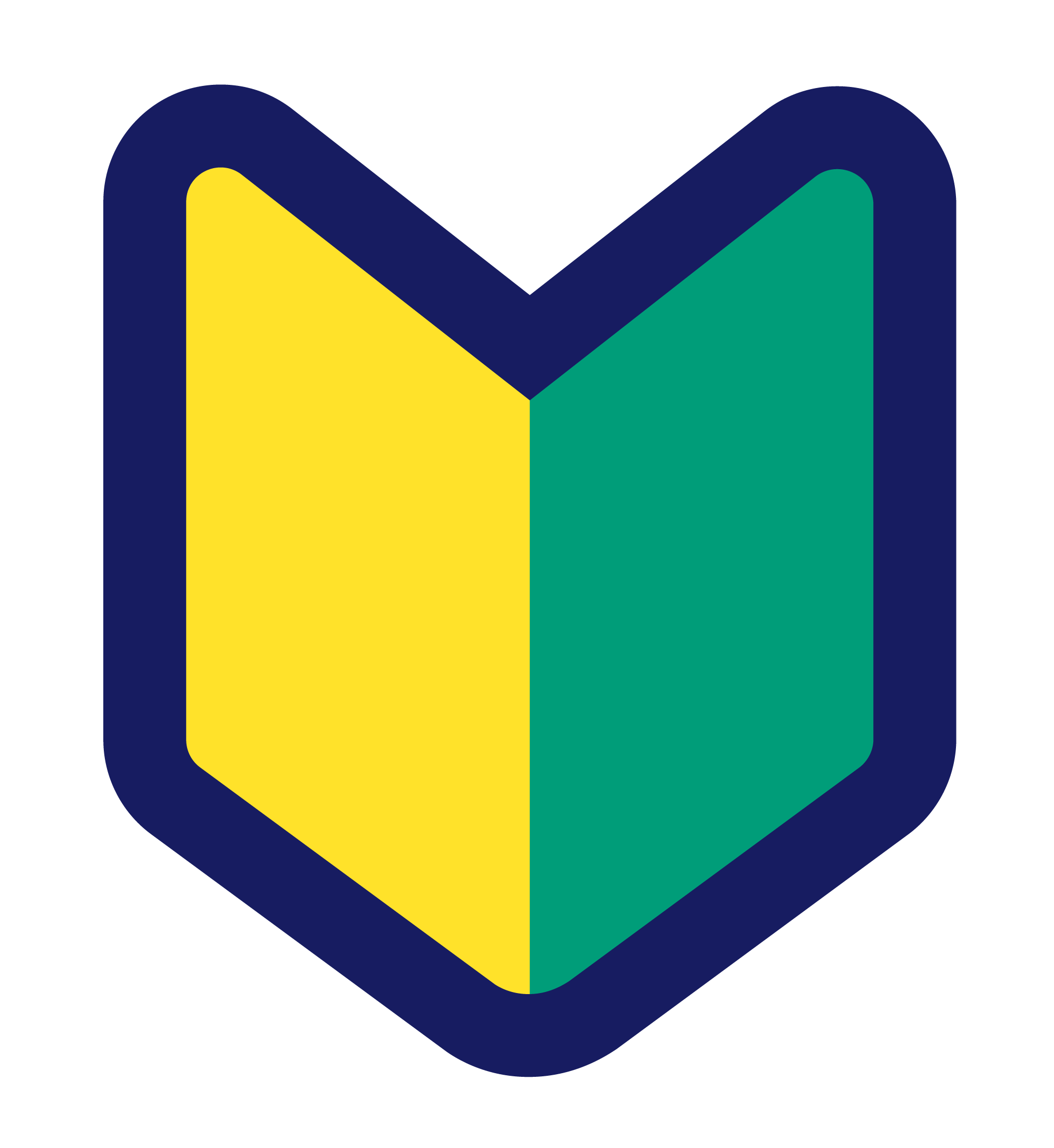 初めての方へ
初めての方へ