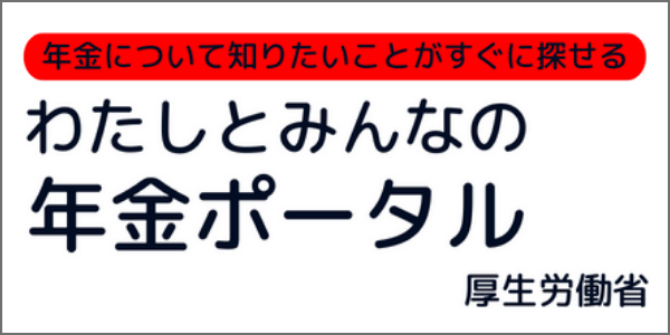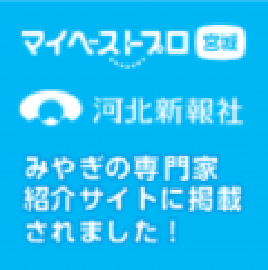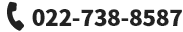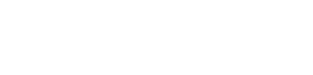「神経症」は障害年金の対象外?制度上の位置づけと例外の可能性を詳しく解説
神経症は障害年金の対象外とされていますが、その理由や背景には明確な制度的根拠があります。本記事では神経症の取り扱いと、例外的に認定される可能性があるケースについて詳しく解説します。
神経症とは?精神疾患との違い
神経症とは、不安や強迫、身体表現性障害、パニック障害など、明確な妄想や幻覚がないものの、日常生活に支障をきたす精神的な症状を指します。近年ではDSMやICDなど国際的な診断基準において「神経症」という分類は用いられず、「不安障害」や「身体症状症」などに細分化されています。
精神疾患の中でも、統合失調症やうつ病などの「精神病性障害」とは異なり、神経症は社会的な適応能力や日常生活への影響が比較的軽微と見なされることが多く、これが障害年金の対象外とされる大きな理由です。
なぜ神経症は障害年金の対象外なのか?
障害年金の認定基準(障害認定基準および精神疾患の障害等級認定基準)では、精神の障害の中でも「統合失調症」「気分障害」「知的障害」「発達障害」「てんかん」「器質性精神障害」などが対象とされており、「神経症」は原則として認定対象外と明記されています。
その理由としては、以下の点が挙げられます。
〇神経症は一般に症状の変動が大きく、長期的な障害状態と評価しにくい
〇日常生活における制限や労働能力への影響が明確に測定しづらい
〇医療や支援により比較的改善が見込めるとされる
例外的に認定される可能性はある?
制度上は「原則として」神経症は対象外とされていますが、実際の運用では症状が重篤化し、他の障害と併存する場合など、総合的に判断されるケースも存在します。
とくに重要なのは、神経症がICD-10(国際疾病分類第10版)における「精神病性障害(例:F2統合失調症群、F3気分障害群)」の病態を明確に示していると医師が判断するケースです。たとえば、神経症の診断であっても、幻覚や妄想等といった精神病性の症状が顕著にみられる場合には、「統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」とされ、障害年金の対象として判断されることがあります。
このような判断がされるには、医師の診断書において、症状が精神病性の病態に分類される下記の具体的な根拠がICD-10コードの分類とともに明示されている必要があります。
- 患者が示す行動や症状が、統合失調症や気分障害のような精神疾患に一致していること。
- 臨床的に確認された幻覚や妄想などの症状が、精神病の基準に適合していること。
- 精神的な症状が、日常生活や社会活動に重大な支障を与えている場合。
申請を検討するなら、専門家への相談が必須
神経症を含む精神的な疾患で障害年金の申請を検討している方は、自己判断だけで手続きを進めるのではなく、社会保険労務士などの専門家に相談することが極めて重要です。
専門家はあなたの症状や生活状況を踏まえて、どのような診断書が必要か、どのように記載を依頼すべきかなどを的確にアドバイスしてくれます。
まとめ
神経症は障害年金の対象とはならないのが原則ですが、例外的に認定される可能性もゼロではありません。しかし、認定のハードルは非常に高く、慎重な準備と専門的な知識が求められます。少しでも疑問や不安がある方は、まずは専門家に相談してみましょう。
必要に応じて、うつ病や発達障害など、神経症と診断が近い疾患との違いについてもご案内できますので、お気軽にご相談ください。

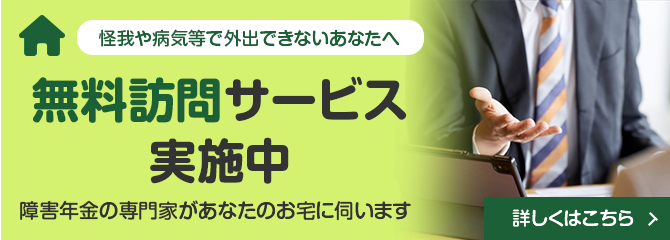
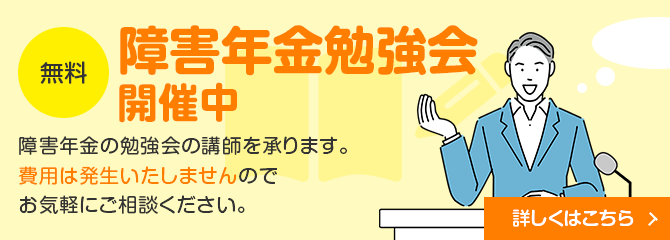

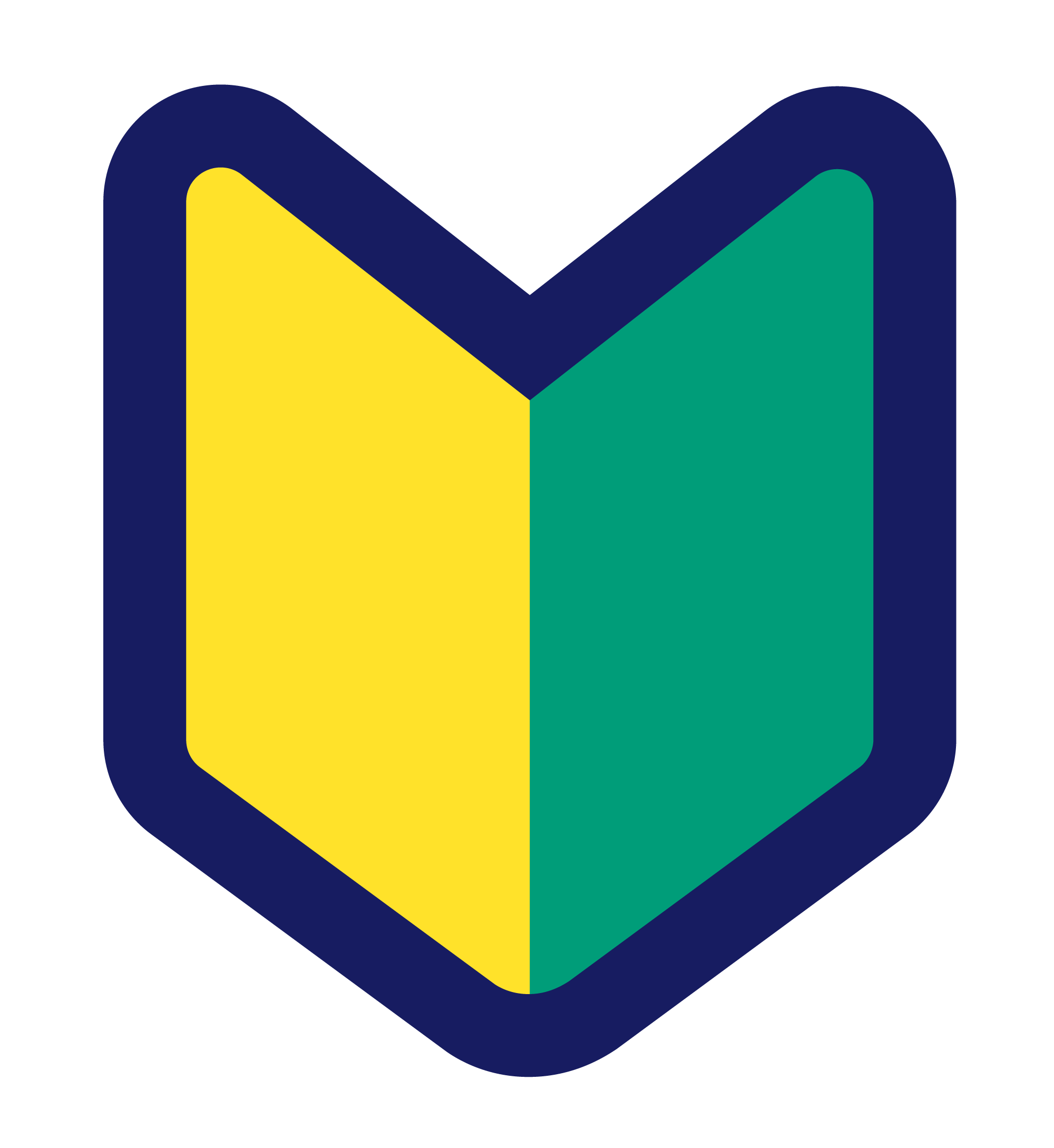 初めての方へ
初めての方へ