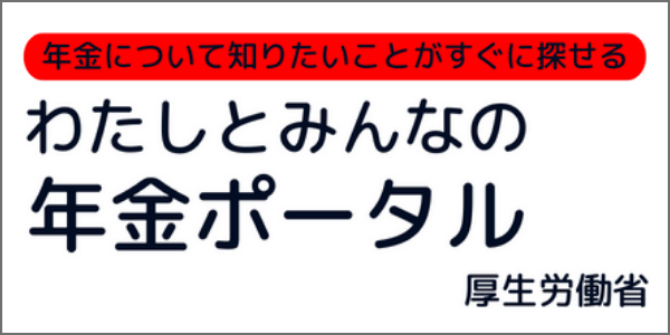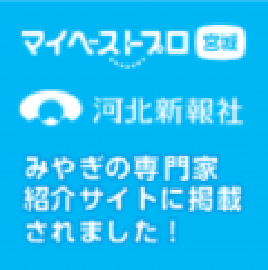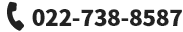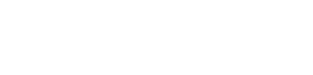障害年金における「初診日」と「相当因果関係」とは?受給に欠かせない重要ポイントを解説
障害年金の申請では「初診日」と「相当因果関係」が重要な要素です。本記事ではその意味と認定されるためのポイント、注意点を専門家がわかりやすく解説します。
障害年金における「初診日」の重要性
障害年金の申請で最も重要な要素の一つが「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。この場合の医師または歯科医師は保健医である必要はありません。この日を基準に、保険料納付要件や障害認定日、さらには年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)も決まるため、正確な特定が不可欠です。
「相当因果関係」とは何か?
相当因果関係とは、前の病気やけががなければ現在の病気が発症しなかったと医学的に認められる関係性を指します。
例えば、最初にA病院で風邪と診断されたものの、症状が改善せず、別のB総合病院で精密検査を受けた結果、肺がんの初期段階であると判明した場合。または、初めて糖尿病でC病院に通院していたが、D眼科で網膜症が合併症として発症した場合などが考えられます。このように、一連の病状の流れの中で密接に関連していると判断されるケースでは、最初に通院したA病院やC病院が初診日となります。
一方で、相当因果関係を否定する見解もあります。具体的には、前の病気やけがをした人が必ずしも別の傷病を発症するわけではないという点です。
例えば、がんと診断された人が精神的に落ち込み、うつ病を発病した場合、このケースでは、がんと診断された人が全てうつ病になるわけではないため、日本年金機構は相当因果関係がないと判断する傾向にあります。
また、他にも主治医が医学的に因果関係をあると診断しても、日本年金機構がそれを否定するケースも多々あります。
なぜ相当因果関係が問題になるのか?
相当因果関係の有無によって、「初診日」が異なることがあります。これが障害年金の保険料納付要件や受給資格に直結するため、非常に重要な判断ポイントです。
相当因果関係を認めてもらうためのポイント相当因果関係が認定されるには、以下のような資料や説明が有効です。
〇医師による医学的見解(診断書の記載内容)
〇病歴・就労状況等申立書の記述
〇継続的な治療の記録
医師の診断書に「以前の病気との医学的因果関係がある」と明記されていることが重要です。自己申告のみでは不十分とされることが多く、裏付け資料の提出が求められます。
医学的に因果関係があっても、障害年金では認められない例
注意すべきなのは、医学的には明確な因果関係があっても、障害年金制度上では「相当因果関係」として認められない場合があるという点です。
以下の病気の組み合わせはその典型で、制度上は「それぞれ独立した傷病」として扱われるため、初診日を遡ることができません。
〇高血圧と脳出血または脳梗塞
〇糖尿病と脳出血または脳梗塞
〇近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神経萎縮
これらは医学的に一定の関係があるとされるケースもありますが、障害年金の審査ではあくまで制度上の判断基準に基づき、相当因果関係は「なし」とされるのが原則です。しかし、個別の詳細な調査が行われることもあります。最終的な判断は日本年金機構が個別に行うため、これらのケースについても、提出資料の内容や治療の経緯によっては再検討されることもあります。
そのため、制度上厳しいとされる組み合わせでも、希望がある場合は病歴の整理や医師の意見書などを整え、専門家とともに戦略的に申請準備を進めることが大切です。
専門家に相談するメリット
「初診日」や「相当因果関係」の判断には医学的・制度的な知識が必要です。特に制度的な知識については、社会保険労務士に相談することで必要な書類の準備や記載のアドバイス、医師やソーシャルワーカーとの連携など、受給の可能性を高める支援が受けられます。
まとめ
障害年金の受給において、「初診日」と「相当因果関係」は制度の根幹に関わる要素です。ご自身のケースでどの日が初診日と認められるのか、相当因果関係が成立するかどうか判断に迷う方は、ぜひ早めに専門家へご相談ください。
あなたの不安や疑問に、しっかりと寄り添いながらサポートいたします。

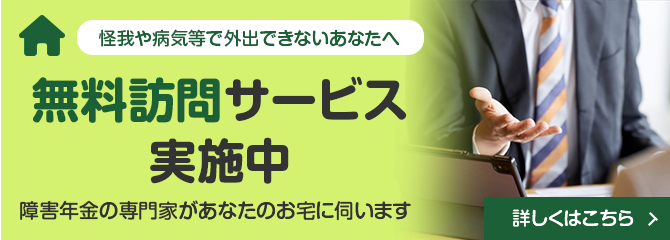
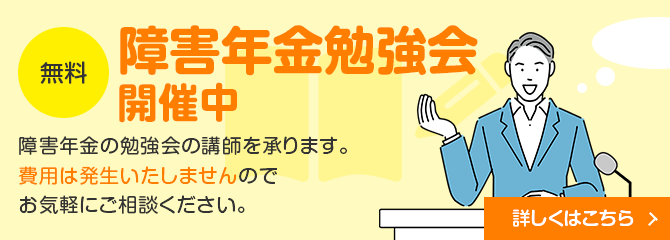

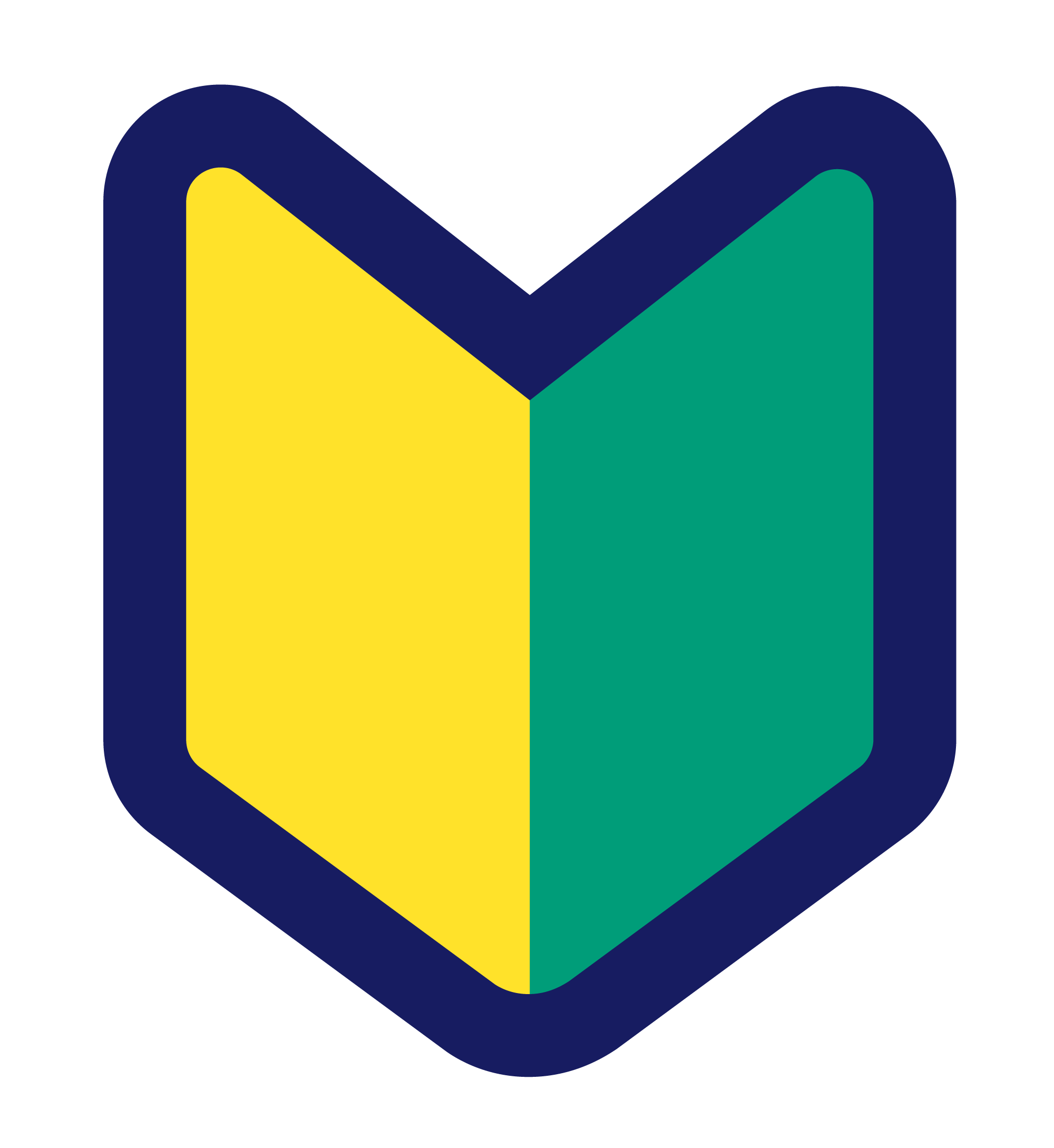 初めての方へ
初めての方へ