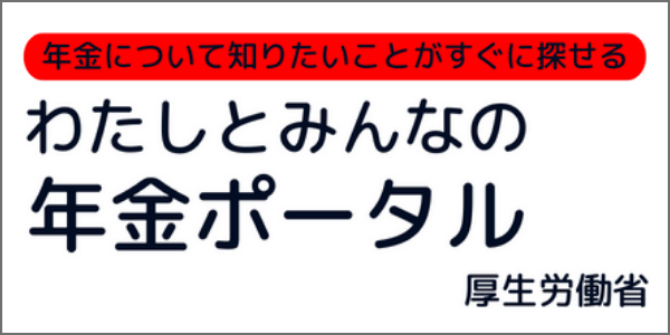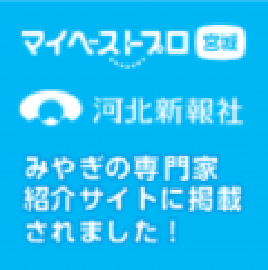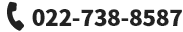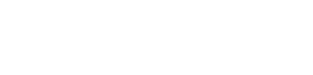「難病」と障害年金との関わりについて受給条件と申請のポイント
難病の定義
難病は、医学的に治療法が確立されておらず、原因も不明なことが多い疾患を指します。厚生労働省では、以下のような条件を満たす疾患を難病と定義しています。
〇発症の頻度が低い
患者数が少なく、人口の一定割合以下にとどまる病気。
〇慢性的に経過する
長期間にわたり患者に影響を及ぼし、完治が難しい。
〇日常生活に支障を来す
身体機能や社会的活動の制限を伴い、生活の質(QOL)が低下する。
〇診断や治療法が未確立
明確な治療法がないため、症状緩和が中心の治療が行われることが多い。
日本では「指定難病」として法律上の特定疾患として扱われるものがあり、約330疾患がこれに該当します。
難病と障害年金の関わり
最初に難病に罹患した事実だけで障害年金が受給できるわけではありません。難病患者が障害年金を受給できるかどうかは、その病状が 障害認定基準 に該当するかによります。障害年金の支給対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 難病が障害年金の対象になる条件
〇初診日の証明
障害の原因となった難病について、初めて医療機関を受診した日が明確であること。
〇障害の程度が認定基準に該当
日常生活や労働能力に大きな制限があり、障害等級(1級、2級、3級のいずれか)に該当する場合。
〇保険料の納付要件を満たす
初診日までに所定の年金保険料を納付していること。特に未納が多い場合、障害年金を受け取ることができません。
2. 難病患者の障害認定基準
難病の症状が障害年金の認定基準に該当するかどうかは、個々の病状や生活状況に基づき判断されます。
〇身体機能の障害
難病による運動機能障害、視覚や聴覚障害、または肢体の障害が認められる場合。
〇精神の障害
難病が精神的な影響を及ぼし、統合失調症や気分障害と同等の状態に該当する場合。(難病を起因とする二次疾患に該当する場合、初診日はメンタルクリニックに最初に通院した日、または難病で通院していた病院で精神症状を訴えた日となることがあります。)
〇日常生活への影響
例えば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの進行性難病の場合、日常生活全般で介助が必要な状態が認定されることが多い。
〇労働能力への制限
難病が進行し、就労が困難になった場合、3級(厚生年金のみ)の認定対象になる可能性があります。
3. 障害年金請求の流れ
〇医療機関での初診日確認
初診日の証明書(受診状況証明書)を取得します。
〇診断書の作成
障害認定基準に基づき、担当医師に診断書を記載してもらいます。
〇必要書類の準備
病歴・就労状況等申立書、年金加入記録、住民票などを揃えます。
〇年金事務所へ申請
書類を提出し、審査を受けます。
4. 難病患者が障害年金を受給するメリット
〇経済的支援
難病の治療費負担軽減に繋がり、生活の安定を図ることができます。
〇社会的支援の拡充
障害年金を受給することで、他の福祉サービス(障害者手帳や介護保険など)も利用しやすくなります。
〇心理的安定
継続的な収入が得られることで、患者本人や家族の精神的負担が軽減されます。
難病患者が障害年金を受給するには、専門的なサポートが重要です。書類の不備や認定基準の理解不足が原因で支給が遅れるケースもありますので、社会保険労務士への相談を検討することをおすすめします。さらに詳細が必要であればお知らせください。

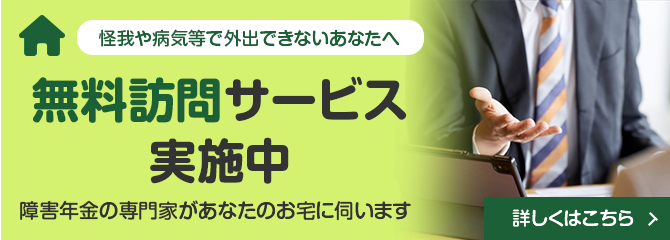
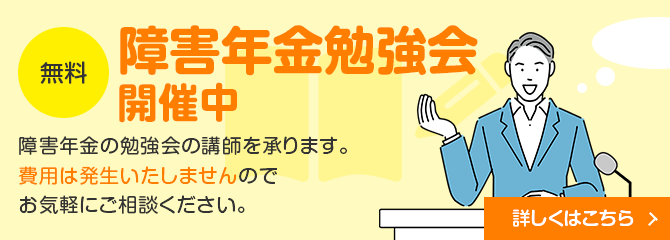

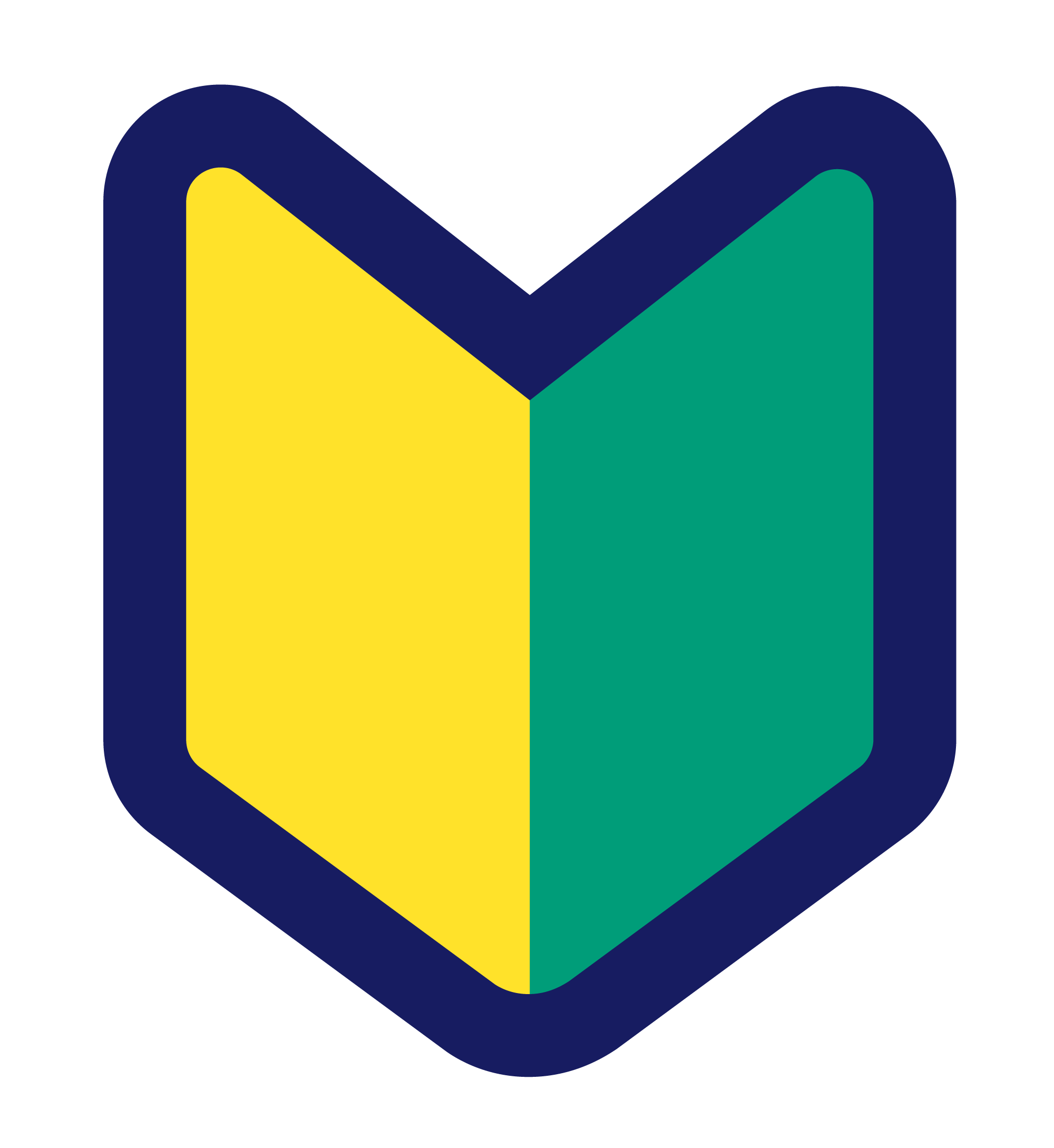 初めての方へ
初めての方へ