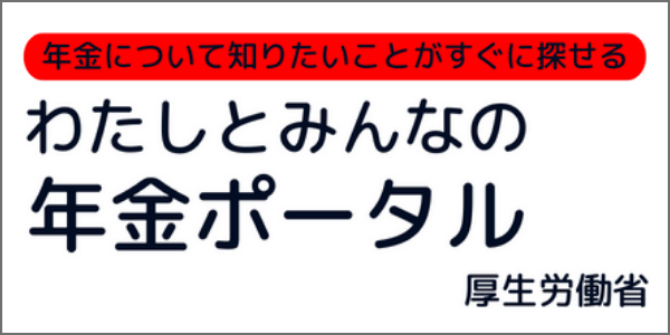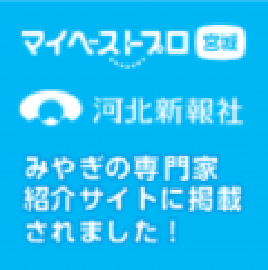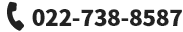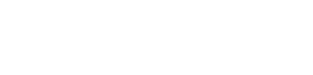「パーキンソン病」と障害年金:受給条件と申請のポイント
パーキンソン病とは
パーキンソン病は、中脳の黒質緻密部に存在するドーパミン作動性ニューロンが変性・脱落することで発症する神経変性疾患です。この結果、基底核回路における神経伝達のバランスが崩れ、運動機能の調節が困難になります。主な症状として、安静時振戦(手足の震え)、筋固縮(筋肉のこわばり)、無動(動作の遅れ)、姿勢反射障害(バランスの悪化)などがあり、非運動症状として自律神経障害、認知機能障害、嗅覚障害、睡眠障害なども見られます。進行性の疾患であり、症状が進むにつれて日常生活や就労に大きな制約を受けることが多くなります。
パーキンソン病で障害年金を受給できるのか?
障害年金は、病気やケガによって生活や就労が困難になった場合に支給される公的年金制度です。パーキンソン病も一定の条件を満たせば受給対象となります。
【受給要件】
1.初診日が確定していること
パーキンソン病の症状が初めて現れ、医療機関を受診した日が「初診日」となります。この日が国民年金の被保険者期間に該当する場合は障害基礎年金の請求対象となり、厚生年金の被保険者期間に該当する場合は障害厚生年金の請求対象となります。
2.一定の障害状態であること
障害認定日以降において、障害等級1級、2級(障害厚生年金の場合は3級も含む)に該当すること。
3.保険料の納付要件を満たしていること
初診日の前日において、一定期間の保険料を納めている必要があります。
パーキンソン病の障害等級と認定基準
パーキンソン病の障害年金の等級は、症状の進行度と日常生活への影響に基づいて決定されます。
1級(障害基礎年金・障害厚生年金)
- 自力での歩行や日常生活の動作がほぼできない。
- 他人の介助が常に必要な状態。
2級(障害基礎年金・障害厚生年金)
- 自力での歩行が困難で、日常生活に著しい制限がある。
- 家族の支援がなければ生活が成り立たない。
3級(障害厚生年金のみ)
- 労働が著しく制限されるが、日常生活はある程度自立している。
- デスクワークなど軽度の作業は可能な場合がある。
申請時のポイント
〇医師の診断書を詳細に記入してもらう
診断書の種類は、肢体の障害用のものになります。パーキンソン病の特徴的な症状(動作緩慢、震え、バランス障害など)を正確に記載してもらいましょう。進行性の疾患であるため、現状だけでなく、今後の予後(見通し)も明記してもらうとよいです。
〇日常生活状況を詳しく記録する
「食事が一人でとれるか」「着替えができるか」「外出の頻度」など、日常生活の支障を具体的に記録しましょう。
〇家族や第三者の証言を活用する
介護している家族や職場の同僚などに、申請書の補助資料として証言を書いてもらうと、より説得力が増します。
まとめ
パーキンソン病で障害年金を請求するためには、症状の進行度と日常生活への影響を正確に伝えることが重要です。特に、診断書の内容が受給の可否を左右するため、医師としっかり相談して作成することをおすすめします。申請が複雑な場合は、社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。
パーキンソン病による障害年金請求についてお悩みの方は、ぜひ専門家へご相談ください。

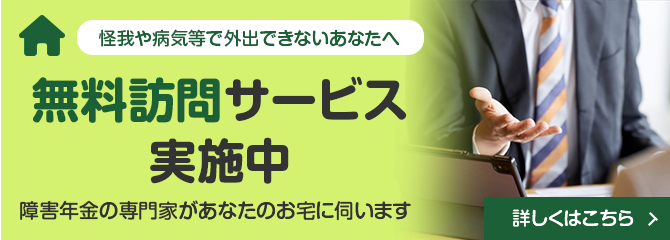
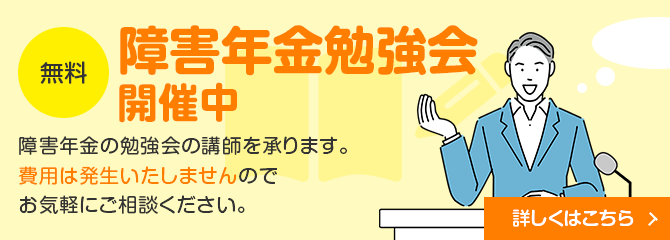

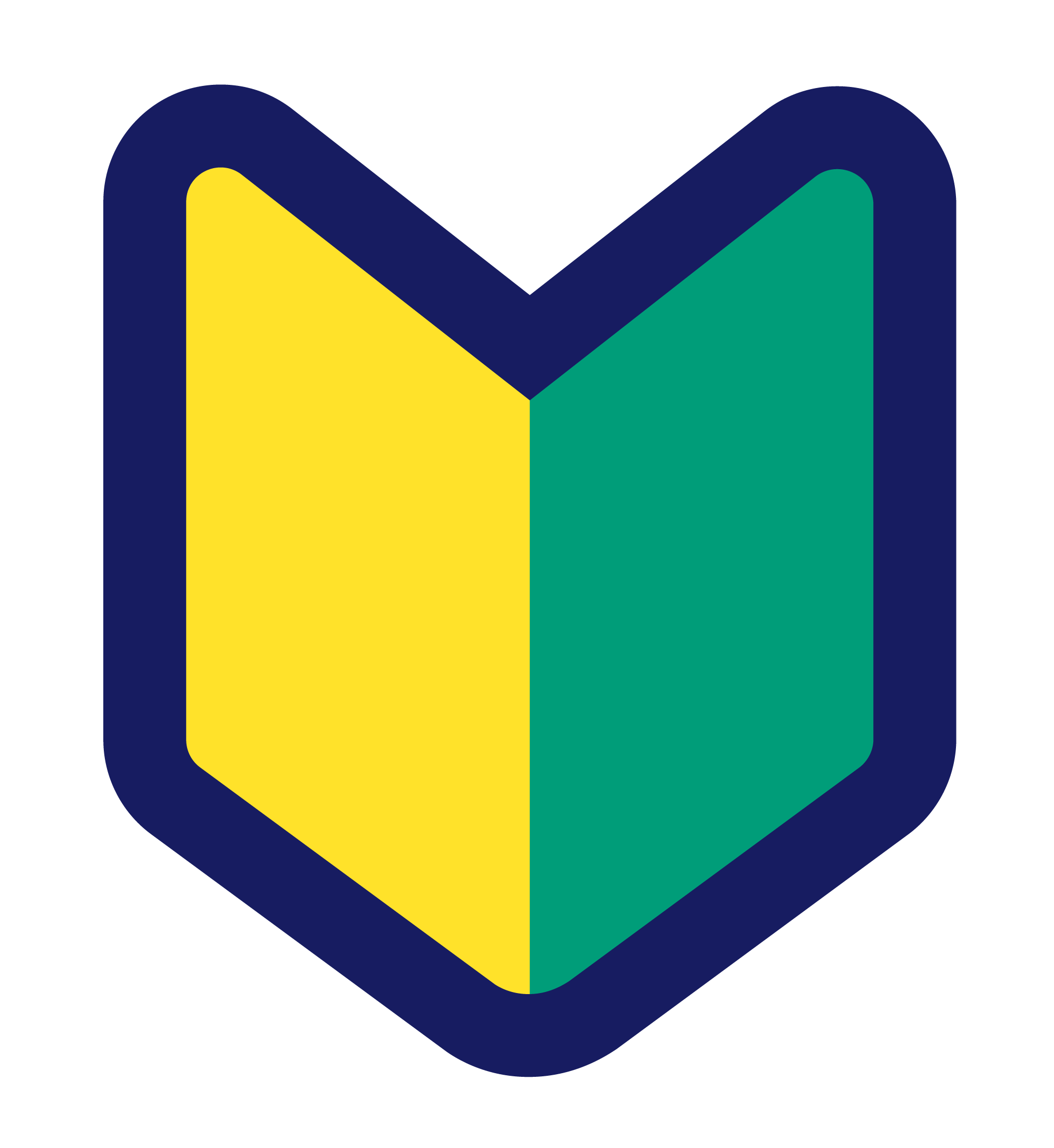 初めての方へ
初めての方へ