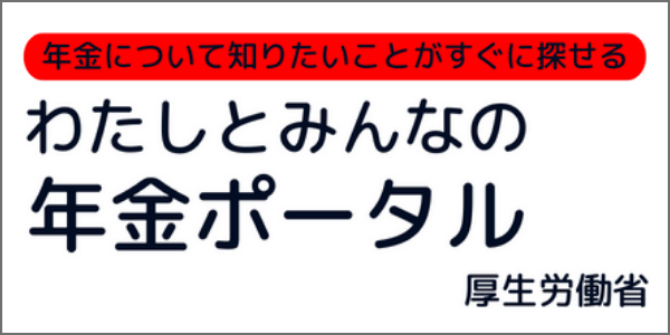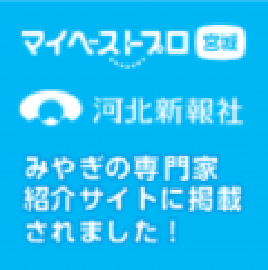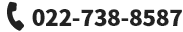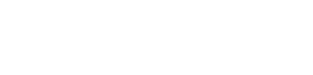「てんかん」と障害年金の受給条件と認定基準を徹底解説
「てんかん」とは?
「てんかん」は、脳の神経細胞が異常に興奮することで発作を繰り返す疾患です。発作の種類は多岐にわたり、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などがあり、症状の重さや頻度も個人差があります。発作は薬物療法で抑えられる場合もあれば、難治性てんかんのように治療が困難なケースもあります。また、発作がない間にも精神神経症状や認知障害が現れることがあり、日常生活や社会生活に影響を与えることが少なくありません。
「てんかん」で障害年金を受給できるのか?
「てんかん」の症状が一定以上の重さであり、日常生活や就労に支障をきたしている場合、障害年金の受給が可能です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれの受給要件を満たす必要があります。
【障害基礎年金(国民年金)】
初診日が国民年金加入期間中であること
障害認定日において1級または2級に該当する障害状態であること
保険料納付要件を満たしていること
【障害厚生年金(厚生年金)】
初診日が厚生年金加入期間中であること
障害認定日において1級、2級、3級のいずれかに該当する障害状態であること
保険料納付要件を満たしていること
「てんかん」の障害等級と認定基準
障害年金の認定基準では、「てんかん」は発作の種類、頻度、発作間欠期の症状によって等級が決まります。
【1級】(障害基礎年金・障害厚生年金)
十分な治療にもかかわらず、以下の発作(AまたはB)が月に1回以上発生し、常時援助が必要な場合
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
【2級】(障害基礎年金・障害厚生年金)
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
【3級】(障害厚生年金のみ)
十分な治療にもかかわらず、AまたはBの発作が年に2回未満、またはCまたはDの発作が月に1回未満であり、労働に制限がある場合
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
※「てんかん発作」については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。
申請時のポイント
【初診日の証明】
障害年金の申請では「初診日」が重要です。最初に「てんかん」の症状が出現し、最初に通院した医療機関の診療記録が必要となります。
【診断書の作成】
診断書には発作の頻度、種類、日常生活への影響、治療状況などが詳細に記載される必要があります。医師と相談し、適切な情報を記載してもらいましょう。
【日常生活状況の説明】
日常生活での困難さを具体的に記載することが重要です。発作による影響や就労の制限について詳しく説明し、客観的な証拠を提出することで審査に有利になります。
受給のためのサポート
障害年金の申請は複雑であり、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。社会保険労務士などの専門家に相談し、適切な書類作成や手続きを進めることをおすすめします。
まとめ
「てんかん」による障害年金の請求は、発作の種類や頻度、発作間欠期の精神神経症状や認知障害がどの程度日常生活や社会生活に影響を与えるかが重要なポイントです。適切な診断書の作成と日常生活状況の説明がポイントとなるため、専門家のサポートを活用しながら申請を進めるとよいでしょう。

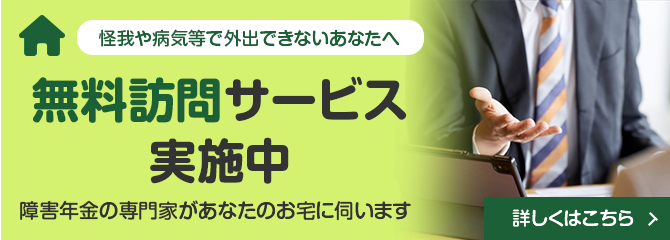
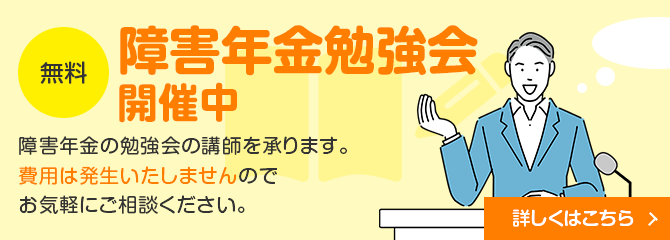

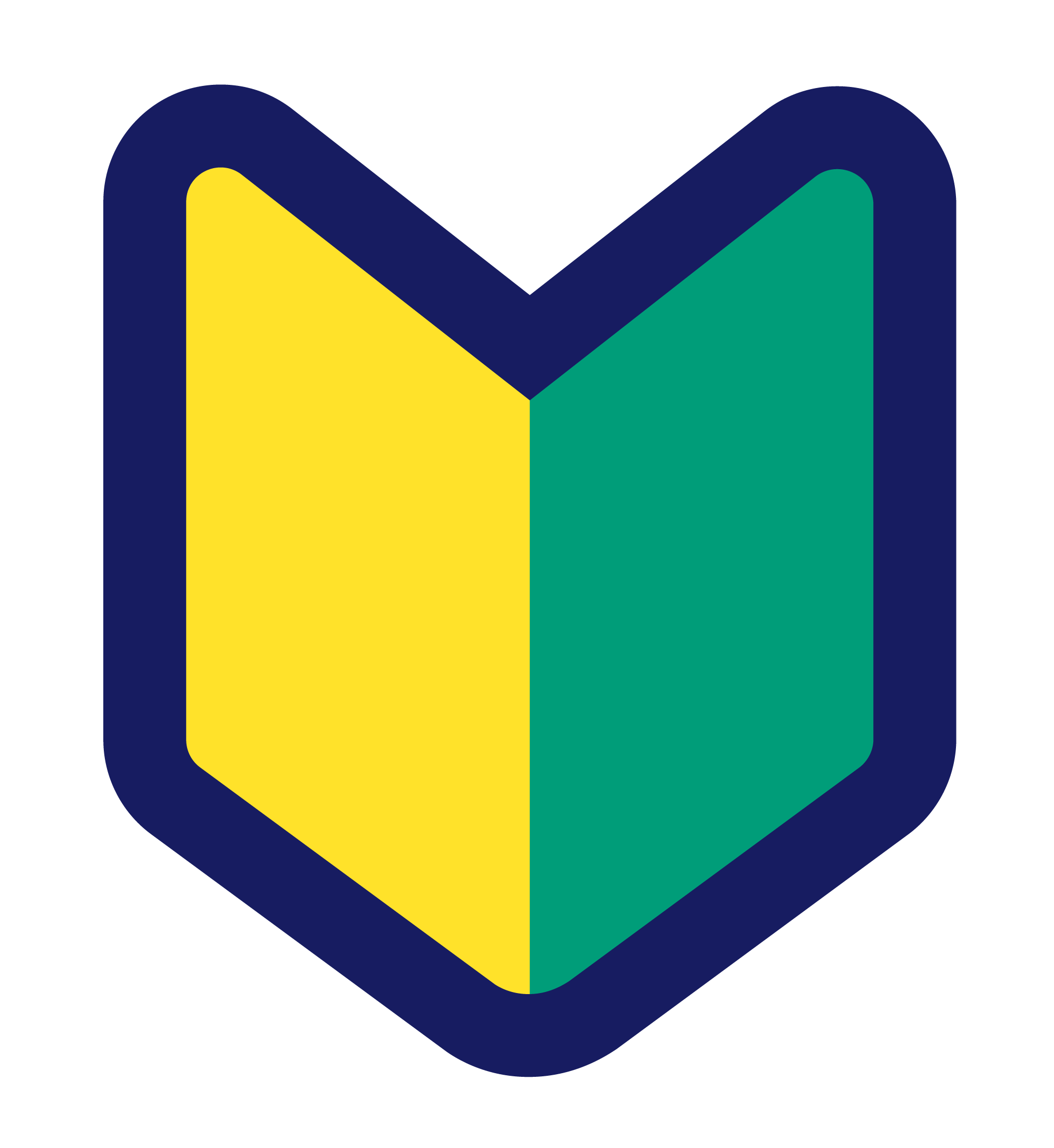 初めての方へ
初めての方へ