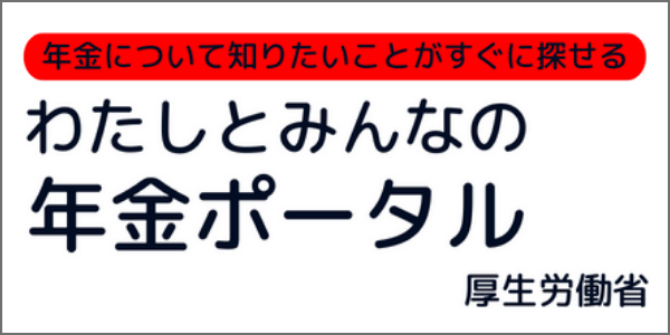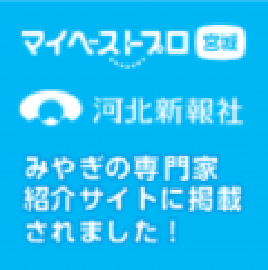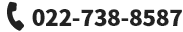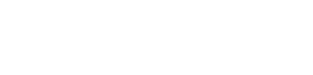虚血性心疾患から低酸素脳症による「高次脳機能障害」で障害厚生年金1級に認定されたケース
相談者
- 性別:男性
- 年齢層:40代
- 職業:会社員
- 傷病名:虚血性心疾患から低酸素脳症による高次脳機能障害
- 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金1級
- 年間受給額:約205万円
相談時の状況
相談者は長年にわたり虚血性心疾患を患い、胸痛発作のたびに常備薬のニトログリセリンを服用していました。当日も胸痛が生じたためニトログリセリンを服用し、一時的に症状は落ち着いたものの、1時間後には玄関で突然倒れ、救急搬送されました。
病院到着時には心肺停止状態であり、蘇生処置が行われましたが、2~3日間は意識が戻りませんでした。医師からは、心肺停止時間が長かったため「低酸素脳症」の可能性があると説明を受けました。その後意識は回復し、家族との会話も可能になりましたが、言動に違和感があり、冗談と本気の区別がつかないなどの症状が現れました。
3か月間の入院後、リハビリテーション目的で転院しましたが、妄想の症状が出現し、「誰もいないのに子供がいる」「警察がいる」などの発言があり、病院内で暴れることがありました。そのため、精神専門の病院へ措置入院となり、約1か月の入院を経て退院しました。
退院後はグループホームに入所しましたが、妄想の症状が継続し、職員が対応しきれず複数のグループホームを転々とすることになりました。現在もグループホームで生活し、施設のスタッフに付き添われながら定期的に通院し、診察と投薬治療を受けている状況でした。
相談から請求までのサポート
相談者の症状は重篤であり、日常生活のあらゆる場面で支援が必要な状態でした。そのため、障害厚生年金1級の取得を目指して申請を進めることとなりました。
初診日を虚血性心疾患で最初に通院した日とするか、今回の救急搬送された日とするかで判断に迷いました。A.虚血性心疾患がなければ低酸素脳症にはならなかったと考えるか、B.虚血性心疾患があっても必ずしも低酸素脳症になるわけではないと考えるかによって、初診日が異なります。今回は、認定日請求が可能となるBの視点に立ち、請求を進めることにしました。ただし、初診日の最終的な判断は日本年金機構の認定医が行うことになります。
高次脳機能障害の特性上、症状の具体的な記載が重要であるため、医師に詳細な日常生活の支障について記載を依頼しました。また、病歴・就労状況等申立書においても、家族や施設職員の証言を基に、妄想、記憶障害、行動障害などの具体的なエピソードを丁寧に記載しました。
特に以下の点を重視しました。
〇 日常生活の支障:トイレのコントロールができずオムツを使用していること、食事管理ができず適切な栄養摂取が困難であること、金銭管理が全くできないことなどを詳細に記載。
〇対人関係の問題:他人の言うことを聞かず、自分の部屋がわからず他人の部屋に入ってしまうこと、他にも多くの問題行動を起こすことなどを明確に記載。
〇社会的適応能力の低下:就労移行支援所に通うも午前中のみで疲れ果て、午後は寝てしまうこと、短時間の作業でも継続できないことなどを記録。
また、医師から記載してもらった診断書には、「日常生活全般にわたり全面的な支援が必要である」との記述もあり、病歴・就労状況等申立書の内容も審査機関が相談者の障害の程度を適切に評価できるよう配慮しました。
結果
申請の結果、障害厚生年金1級が認定され、年間約205万円の受給となりました。
これにより、相談者は安定した経済的支援を受けることが可能となり、今後も施設での生活を継続しながら適切な医療・介護を受けることができます。家族からも「障害年金の支給が決まり、金銭的な不安が軽減されて本当に助かった」との感謝の言葉をいただきました。
現在もグループホームで生活しながら、施設スタッフの支援のもとで通院・服薬治療を続けています。今後も生活の安定と適切な支援を受けながら、できる限り快適に過ごせる環境を整えていくことが課題となります。
このケースは、高次脳機能障害による認知機能の低下、行動異常、日常生活全般の支障が詳細に証明されたことにより、障害厚生年金1級の認定につながりました。高次脳機能障害は外見では分かりにくい障害ですが、具体的なエピソードを丁寧に記録し、医師の診断書と申立書を充実させることが重要です。
障害年金の申請を検討されている方は、専門家の支援を受けながら、適切な書類作成と申請手続きを進めることをおすすめします。

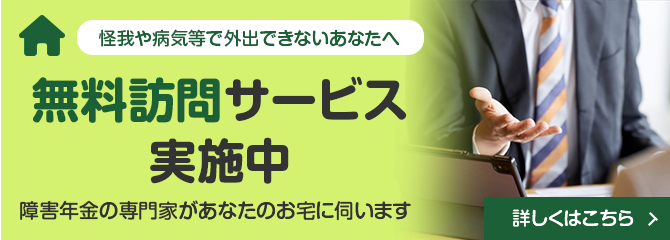
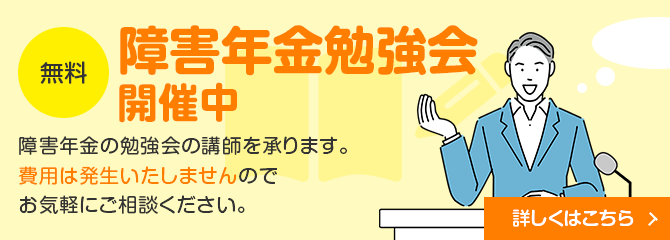

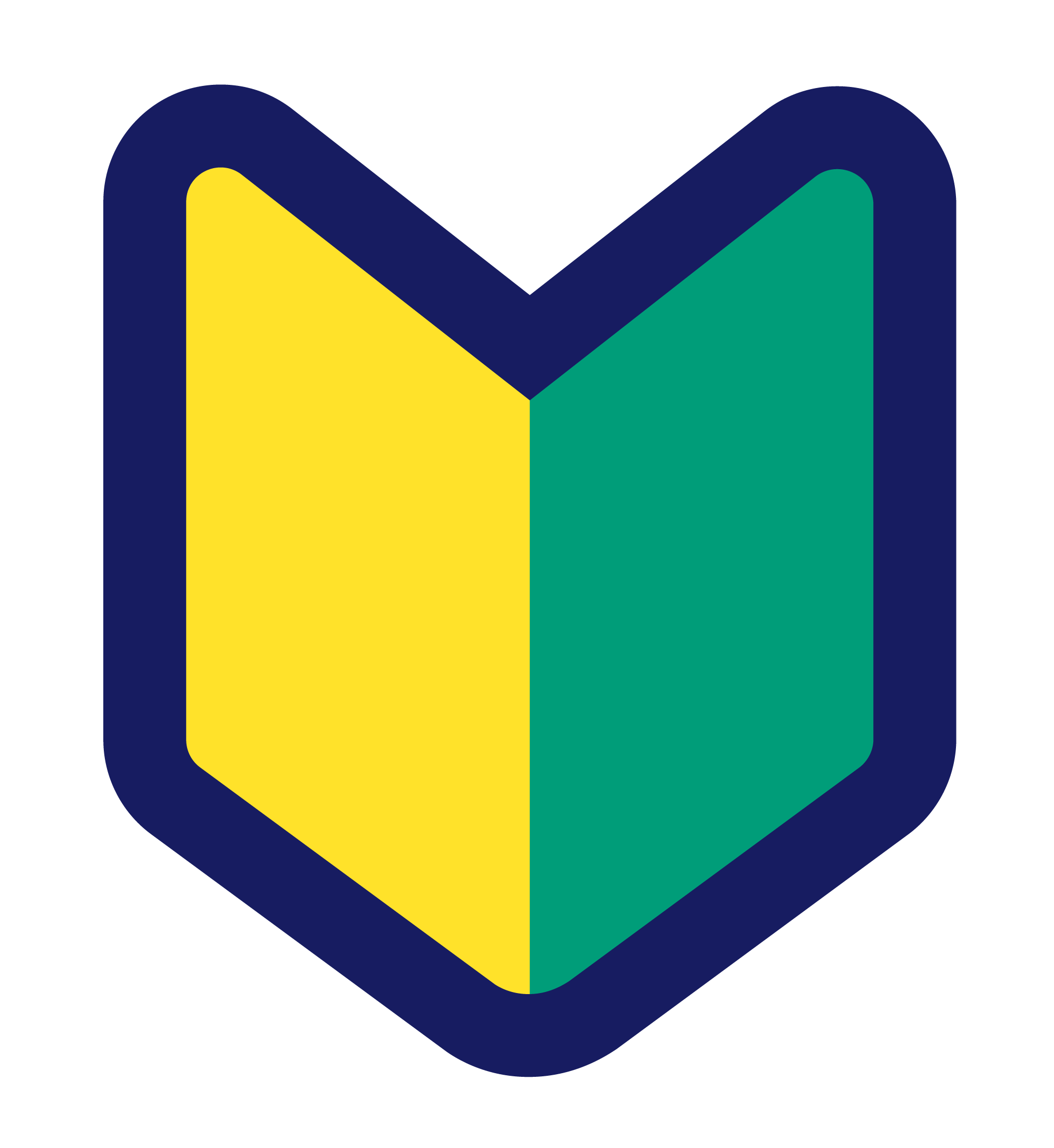 初めての方へ
初めての方へ