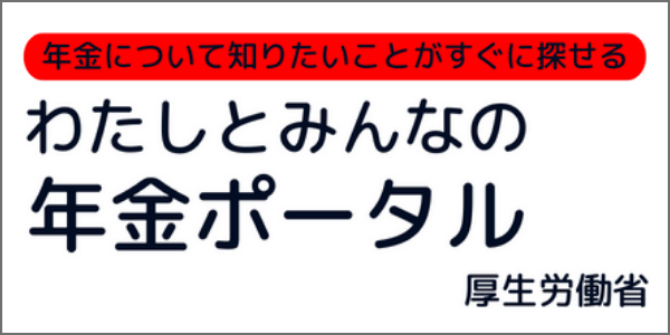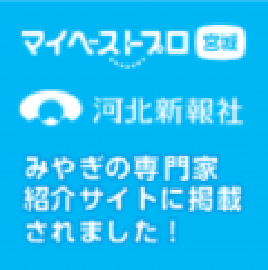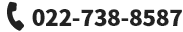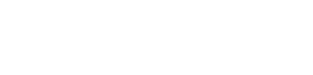脳梗塞を原因とする「高次脳機能障害」と「音声・言語機能障害・失語症」の後遺症で障害厚生年金1級を取得、年間約223万円の受給となったケース
相談者
- 性別:男性
- 年齢層:50代
- 職業:会社員
- 傷病名:脳梗塞の後遺症による高次脳機能障害、音声・言語機能障害、失語症
- 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金1級
- 年間受給額:約223万円
相談時の状況
相談者は職場で倒れ、救急搬送されました。その後、脳梗塞と診断され、「高次脳機能障害」「音声・言語機能障害」「失語症」「右半身麻痺」などの後遺症が残りました。急性期治療の後、リハビリを続けながら回復を目指しましたが、「右半身麻痺」以外は完全な回復には至りませんでした。
障害認定日以降もリハビリを継続しており、日常生活においては多くの支援が必要な状況でした。特に以下のような課題がありました。
記憶障害の影響で、日常的な出来事をすぐに忘れてしまい、言語障害により会話の理解や意思疎通が困難な状況でした。また、身の回りの管理が難しく、金銭管理や買い物も一人で行うことができませんでした。勤務先が大手企業のため職場の配慮により復職はできたものの、単純作業しかできず、以前の職務に戻ることは不可能でした。さらに、自動車の運転ができないため、通勤には妻の送迎が必要であり、服薬管理も自分ではできず、妻の援助が不可欠な状態でした。
これらの理由から、障害年金の申請を検討することになりました。
相談から請求までのサポート
相談者の症状は多岐にわたっており、申請に際して以下の点に特に注意を払いました。
〇診断書と病歴・就労状況等申立書の整備
初診日を証明するため救急搬送された病院から「受診状況等証明書」を取得し、診断書は、「精神の障害用」と「言語機能障害用」の2種類を用意し、主治医に脳梗塞による高次脳機能障害と言語機能障害の影響を詳細に記載していただくように脳神経内科の主治医に依頼しました。
「病歴・就労状況等申立書」には、記憶障害や注意障害、失語症の影響で、日常生活に大きな支障が生じていることを詳細に記載しました。また、金銭管理ができず、通院や服薬管理においても妻の支援が不可欠である点を強調しました。さらに、職場復帰後も単純作業しかできず、以前の職務に戻ることが不可能な状況であることを明確に記載しました。
〇申請書類の作成と提出
診断書は、「精神の障害用」と「言語機能障害用」の2種類を提出し、「病歴・就労状況等申立書」において、日常生活や就労の困難さを具体的に整理し、医師の診断書と内容を統一させることで、審査機関に正確な状況を伝えられるよう努めました。また、申請書類の整合性を確認し、不足部分の補完や必要な修正を施しました。また、高次脳機能障害の影響を的確に伝えるため、障害年金請求時には神経心理学的検査結果も提出しました。
結果
申請の結果、障害厚生年金1級が認定され、年間約223万円の受給が決定しました。
これにより、相談者は経済的な安定を得ることができ、引き続き治療とリハビリに専念できる環境を整えることができました。現在も妻の支援を受けながら生活しており、定期的な通院を続けています。
今回のケースでは、高次脳機能障害による日常生活への影響が大きく、適切な書類の作成と医師の協力が重要なポイントとなりました。障害年金の申請を検討している方は、専門家のサポートを受けながら進めることで、よりスムズに申請を行うことができます。

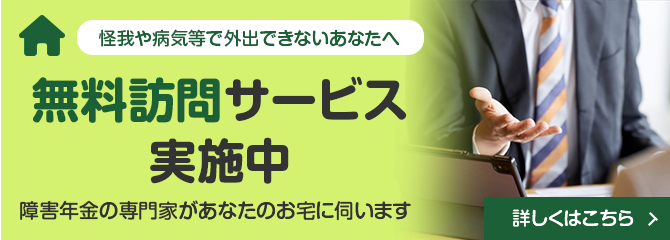
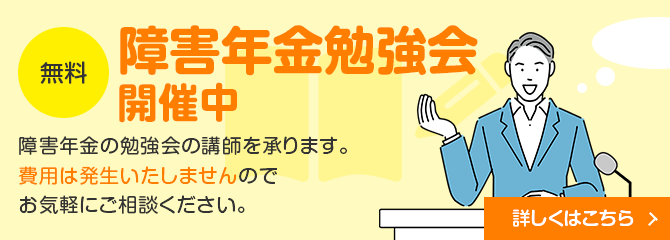

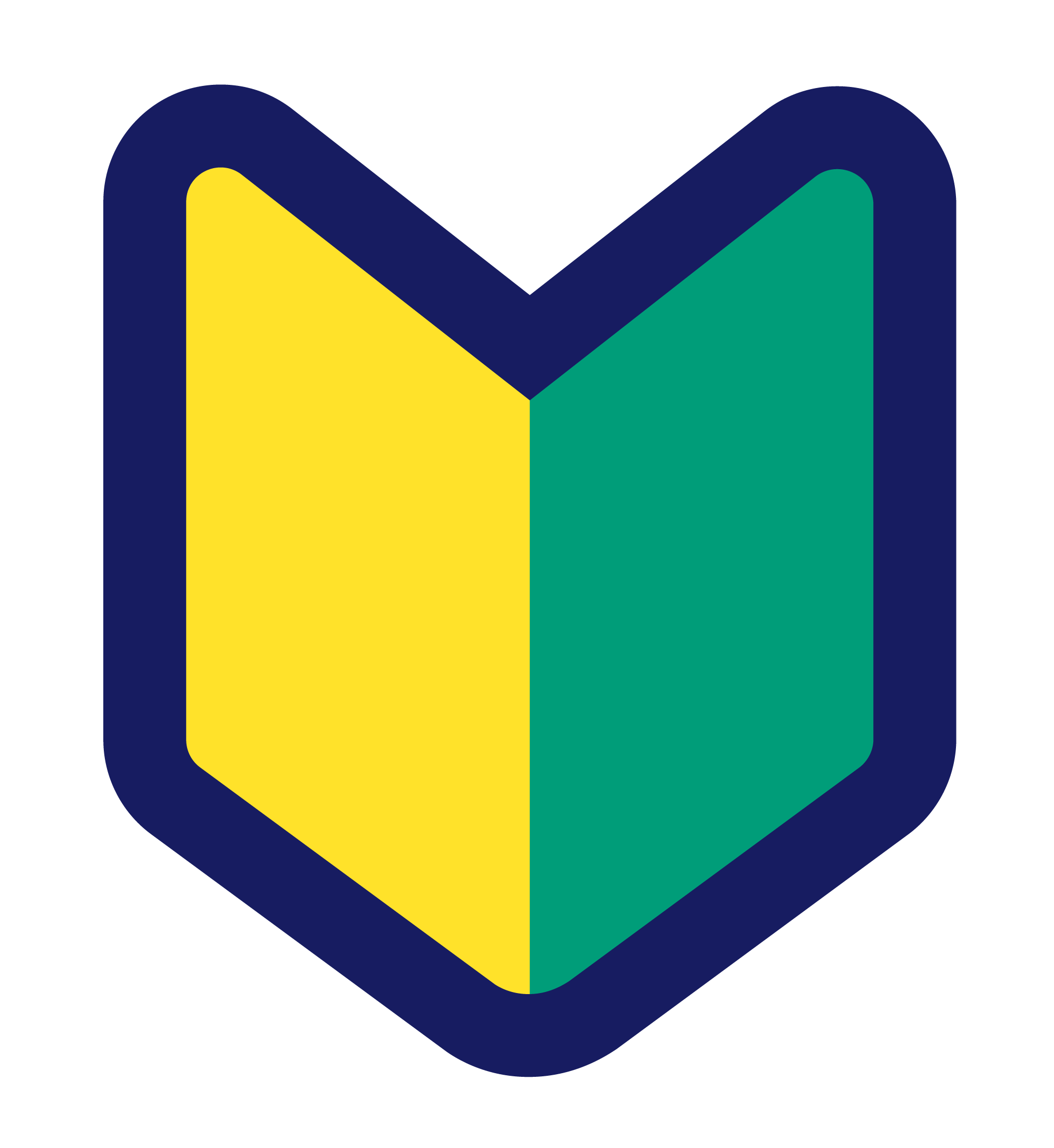 初めての方へ
初めての方へ