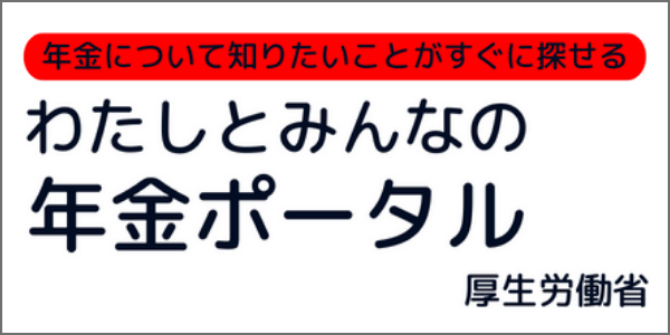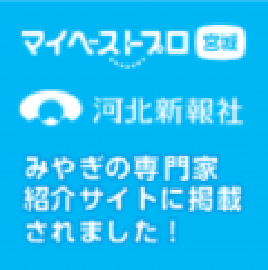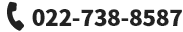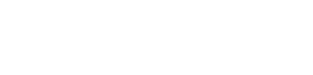「高次脳機能障害」で障害基礎年金2級を受給、年間約83万円が認定されたケース
相談者
- 性別:男性
- 年齢層:20代
- 傷病名:高次脳機能障害
- 決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
- 年間受給額:約83万円
相談時の状況
相談者は幼少期に脳腫瘍および水頭症に対する大手術と放射線治療を受けたことで、後遺症として高次脳機能障害を発症されました。手術後は失語や運動機能喪失により、言葉すら発せない日々が続きました。
その後も治療を継続しながら成長されましたが、日常生活や学校生活において様々な困難が顕在化していきます。小中高を通じて集団生活への適応ができず、いじめや孤立に悩み、最終的には高校を中退。その後高卒認定を取得後、大学進学となったが人間関係のトラブルが続き、感情のコントロールが困難となって暴言や暴力が頻発。家族との関係も著しく悪化し、ついには筆談でしか意思疎通ができないほどの状態に陥っていました。
その後、A総合病院にて正式に「高次脳機能障害」の診断を受け、怒りや衝動性、記憶障害、判断力の欠如といった症状はすべて障害に起因するものであると明確に示されました。家庭内暴力や感情爆発、金銭管理の不能、身辺自立の欠如、コミュニケーションの困難といった多面的な問題から、家族による常時の支援が必要な状況でした。
相談から請求までのサポート
相談者の状態は非常に複雑で、家族からも「暴力や破壊行為が日常化しており、いつ近隣トラブルや事件に発展するか分からない」と不安の声が上がっていました。まずは、診断書の内容が高次脳機能障害による「日常生活能力の全般的な低下」として適切に記載されるよう、A総合病院のソーシャルワーカーとの連携を図りました。
また、「病歴・就労状況等申立書」には、幼少期から現在に至るまでの経過を詳細に記載。とくに以下の点を丁寧に補足することで、障害の重症性を具体的に伝えるよう努めました。
- 感情のコントロールができず、家族への暴言・暴力が頻繁に発生していること
- 食事、入浴、着替えなど、基本的な日常生活動作が自立して行えず、家族の介助が常に必要なこと
- 金銭管理が一切できず、過去に詐欺被害にも遭っていること
- 公共交通機関の利用や行政手続きができず、社会性が著しく制限されていること
- 本人は障害を認識できず、自らの困難を適切に訴えることもできないこと
- これらの内容を一つ一つ整理し、障害年金の審査基準に則った形で申請書類を構成しました。
結果
申請の結果、高次脳機能障害により障害基礎年金2級が認定され、年間約83万円の受給が決定しました。ご家族は「生活の不安が少し軽くなり、今後の支援体制を考える上でも大きな一歩となった」とおっしゃっており、申請が精神的な支えにもなったようです。
現在は、主治医の指導のもとで継続的な医療的支援を受けながら、少しでも穏やかに生活できる環境の構築に向けて、家族とともに取り組まれています。
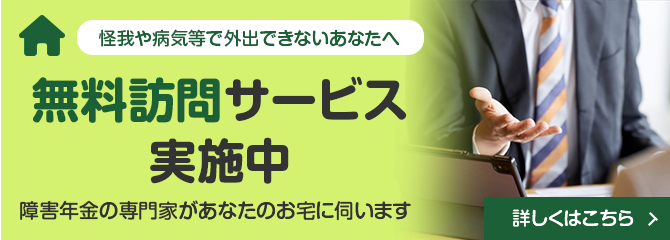
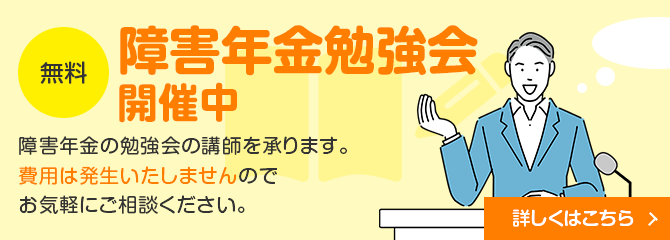

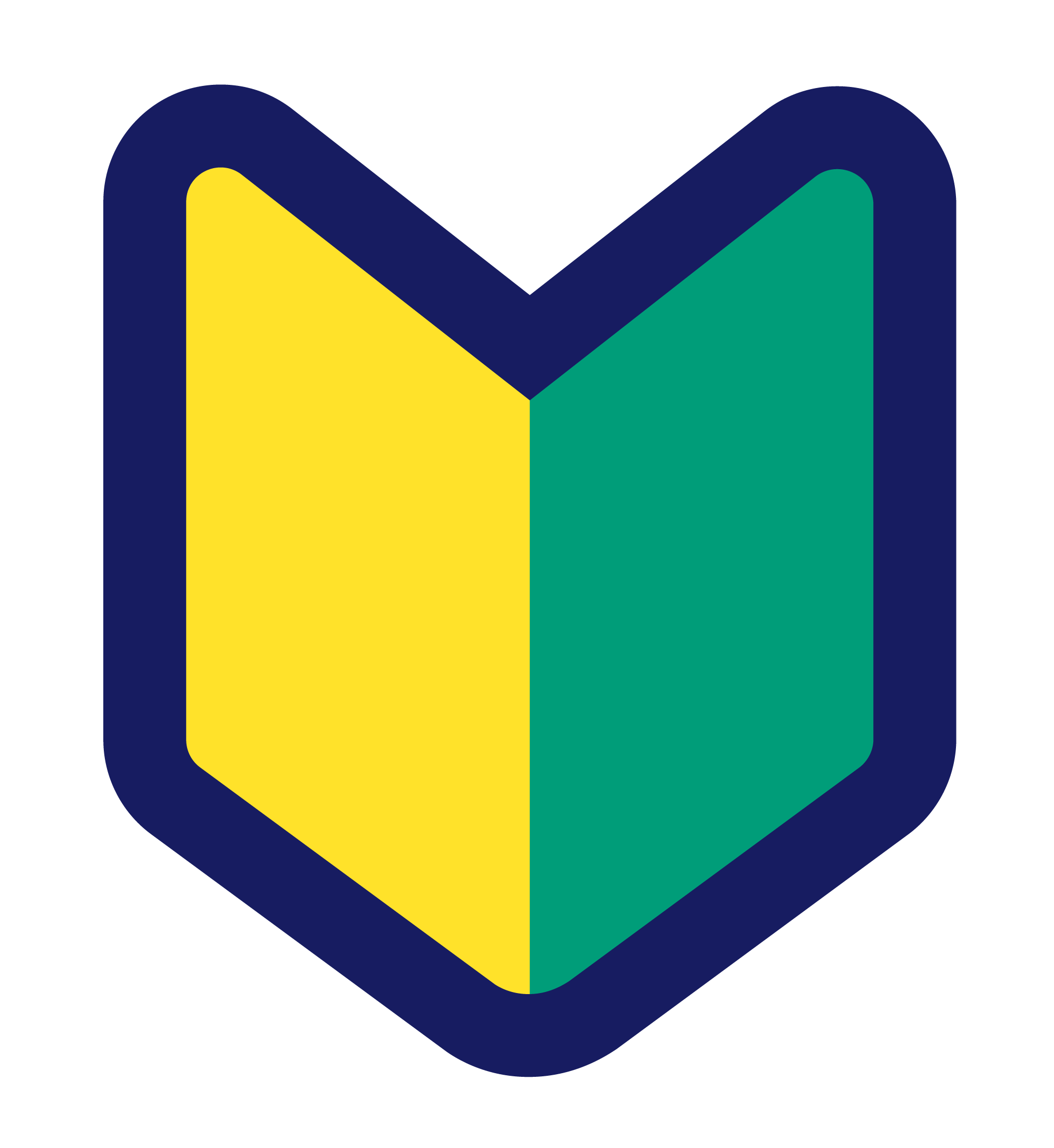 初めての方へ
初めての方へ